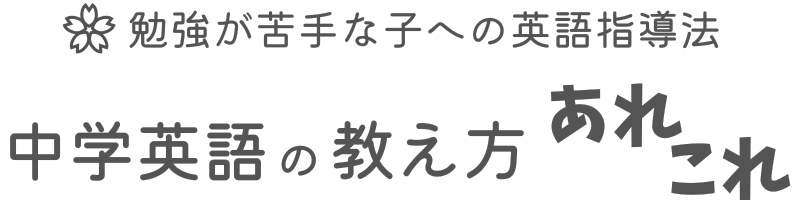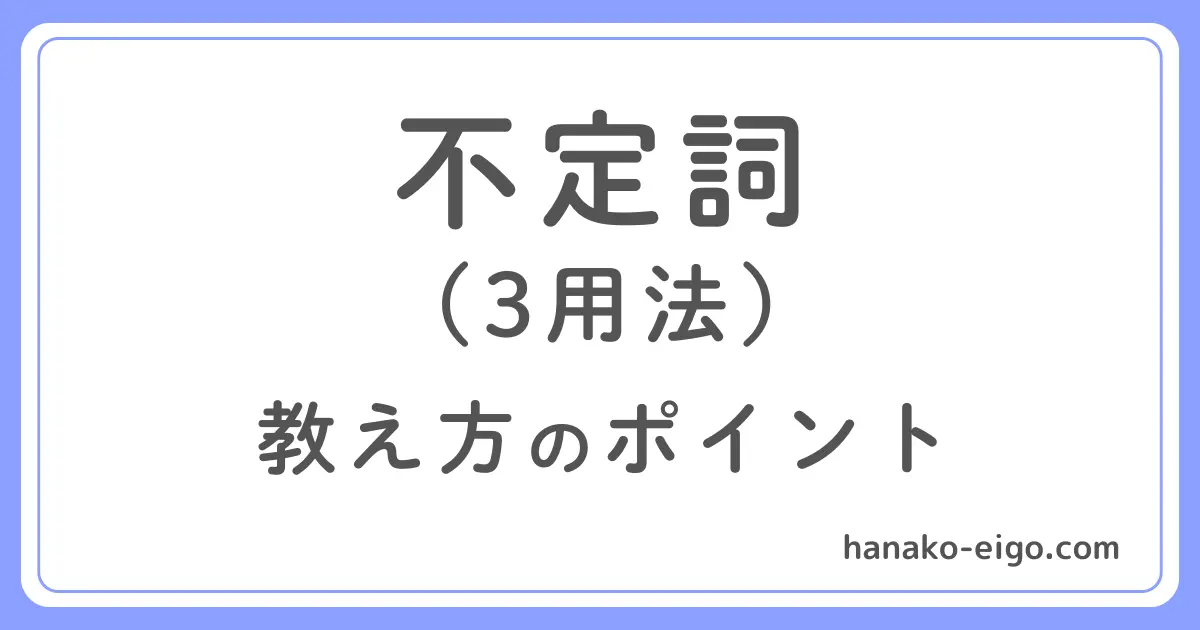「勉強が苦手な中学生に不定詞を教えるには、どうすればいい?」「問題集の解説どおりに教えても、なかなか理解してもらえない」
そうお悩みの方に、不定詞を教えるときのポイントを3つご紹介します。
どれもちょっとしたことなのですが、それを実践すれば勉強が苦手な子も不定詞を理解しやすくなりますよ。
また記事の後半では、副詞的用法・形容詞的用法・名詞的用法それぞれについて、教えるときの注意点をご紹介します。
不定詞を教えるときのポイント
勉強が苦手な子に不定詞を教えるときのポイントは、3つあります。
- 用法の名前を教えるのは後回しにする
- 「何を学ぶのか」を平たく説明する
- ウォーミングアップをする
用法の名前を教えるのは後回し
副詞的用法・形容詞的用法・名詞的用法という用語は問題集に必ずと言っていいほど載っています。ですので、「子どもに絶対覚えさせなければ!」と思ったりしますよね。
でも、じつは用法名を覚えていなくても、不定詞の問題を解くことはできます。
唯一解けないのが、「次の不定詞は何用法か答えなさい」という問題です。でも、用法名についての問題は“おまけ”のようなもの。文法問題のメインではありません。
ですので、「用法名は必ず覚えるべきだ」というわけではないのです。
勉強が苦手な子の場合、用法名を覚えるのはむしろ後回しにして、「訳し方」や「文の作り方」にフォーカスしたほうがいいです。その2つを覚えるのだけでも十分大変ですからね。
文法問題を解くのに欠かせない知識(訳し方・文の作り方)を優先して身につけてもらう。そしてもし余裕があれば用法名も教える。
そのくらい割り切ったほうが、子どもが不定詞の問題を解きやすくなります。
「何を学ぶのか」を平たく説明する
文法を教えるときは、まず「今回はどんなことを学ぶのか」について説明しますよね。そのとき、次のような問題集の解説を読み上げるのはオススメしません。
「形容詞的用法では不定詞が形容詞の働きをし、名詞を後ろから修飾する」
いきなりこういう抽象的なことを言われても、勉強が苦手な子は「自分がこれから何を学ぶのか」をイメージできないでしょう。
そして「何を学ぶのか」が分からないまま解説を聞き続けても、なかなか頭に入ってきません。
ですので各用法の解説に入る前に、「何を学ぶのか」を平たく説明することが大事です。
今日は「~するべき」という表現を覚えよう。
たとえば修学旅行で人気の京都を思い浮かべてほしい。京都は、「見るべきお寺」とか「買うべきお土産」がたくさんあるね。
そういう、「~するべき」という言い方を学習しよう。
お子さんの修学旅行先に合わせて、地名や内容を変更してください。なじみのある地名のほうが子どももイメージしやすいですからね。
今日は、「~するために」という表現を覚えよう。
たとえば、明日、ショッピングモールに行くとするよ。なんのために行くかというと、「ペンを買うために」とか「ゲームをするために」とか、いろいろ目的があるよね。
そういう、「~するために」という言い方を学習しよう。
今日は、「~すること」という表現を覚えよう。これは普段、誰もがよく口にしている表現だよ。
たとえば、「動画を見ることは楽しい」とか、「私の夢はパティシエになることだ」とか言ったりするよね。そういう、「~すること」という表現を学習しよう。
このように具体的に説明すれば、「何を学ぶのか」について子どもがイメージしやすくなります。そしてちゃんとイメージできれば、その後の解説も理解しやすくなるでしょう。
ウォーミングアップをする
「不定詞を使った文」の作り方に入る前に、ウォーミングアップとして「不定詞の作り方」だけにフォーカスします。〈to + 動詞の原形〉というカタマリに慣れるのです。
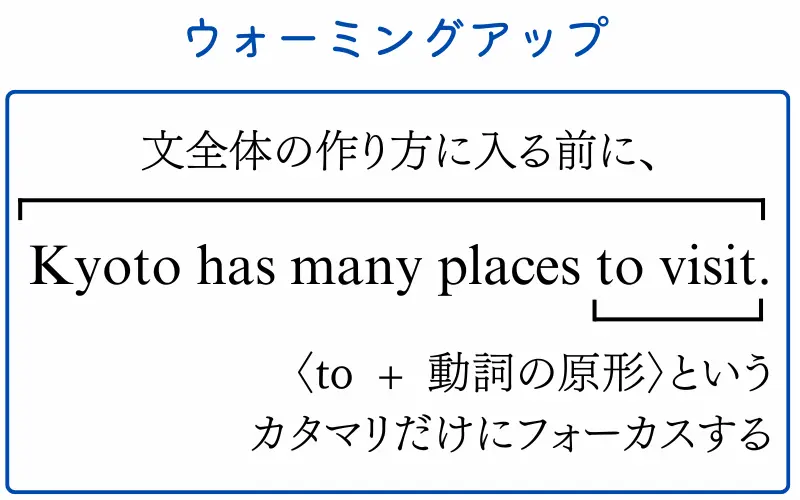
ウォーミングアップが必要なワケ
「不定詞のカタマリに慣れる」というウォーミングアップがないまま文全体を作る場合、次のようなマルチタスクをしないとなりません。
- 不定詞で使われている(見慣れない)動詞を書き写しながら、
- 〈to + 動詞の原形〉というカタマリを作り、
- 文全体の作り方も覚える
勉強が苦手な子はそもそも動詞を覚えていないことがよくあるため、動詞を書き写すことだけでも大変です。そういう状態で文全体の作り方まで覚えようとしても、なかなか頭に入りません。
ですので、まずは「動詞のおさらいをして、〈to + 動詞の原形〉というカタマリに慣れる」というウォーミングアップをしておきます。
ウォーミングアップの手順
(1)
まず、不定詞の単元でよく出てくる動詞の「読み方」と「意味」をおさらいします。
たとえば形容詞的用法の場合、問題集によく出てくるのは see, do, visit, read, buy, eat, drink などです。
(2)
動詞の「読み方」と「意味」をおさらいしたら、次はそれらの動詞を使って〈to + 動詞の原形〉というカタマリを作る練習をします。
たとえば形容詞的用法の場合、「~するべき」というカタマリを作ります。
見るべき ( to )( see )
買うべき ( )( )
訪れるべき ( )( )
こうやって不定詞のカタマリにあらかじめ慣れておけば、文全体の作り方も頭に入りやすくなるでしょう。
「動詞の意味が分からなくてつまずく」ということがないので、文全体の語順に意識を向けやすくなります。
そして語順を意識できれば、不定詞を使った基礎的な文をきっと書けるようになりますよ。
以上、副詞的用法・形容詞的用法・名詞的用法に共通のポイントを3つご紹介しました。
各用法を教えるときの注意点
このセクションでは、用法ごとの注意点をお伝えします。
「目的」を表す副詞的用法(~するために)
この用法で子どもがつまずきやすいのが、「日本語の文の構造を把握する」という点です。
英作文や並べ替え問題に取り組むには、日本語の文を読み、
- 「だれだれは、〇〇する」の部分はどこか?
- 「~するために」のカタマリはどこか?
……を把握する必要があります。これは勉強が苦手な子にとって必ずしも簡単ではありません。
そこで、日本語の文の中から「~するために」のカタマリを見つけ出す、という練習をします。
「私はおじに会うために東京へ行った」
この文の中で「~するために」のカタマリを□で囲もう。
この例文の場合、「おじに」を抜かして「会うために」とだけ答える子もいます。最初はそうやって間違う子も、何回か練習すれば要領をつかんでくるので大丈夫。あせらずに取り組んでみてくださいね。
「~するために」のカタマリを見つけたら、次の指示を出します。
□で囲んでいない部分、つまり、「だれだれは、〇〇する」という部分をまず英語に訳そう。そのあと「~するために」のカタマリを付け加えるよ。
このように、日本語の文の構造を意識できれば、英作文問題なども解きやすくなるでしょう。
副詞的用法(~するために)の教え方をもっと詳しく知りたい方は、「不定詞の副詞的用法|勉強が苦手な子がつまずく原因と対策は?」をご覧ください。
「感情の原因」を表す副詞的用法
この用法では、不定詞を使って「感情の原因」を表しますよね。
(例) I’m surprised to hear the news.
勉強が苦手な子にとって、いきなり文全体を書くのは大変です。そこで、3段階に分けて少しずつ教えていきます。
(1) 「感情」を表す単語に慣れる
勉強が苦手な子の場合、そもそも「感情」を表す英単語(surprised, excited, sorry など)をあまり覚えていません。
ですので、「感情の原因」を表す方法について解説する前に、まずは「感情」そのものを表す単語を復習しておきましょう。
復習しておかないと、「感情」を表す単語を覚えながら、同時に「感情の原因」を表す方法も学ばないとなりません。そういうマルチタスクは大変なので、まずは「感情」を表す単語に慣れるのがオススメです。
(2) 不定詞のカタマリに慣れる
「~して(驚いている)」「~できて(うれしい)」など、感情の原因を表す不定詞に慣れてもらいます。
問題集によく出てくるパターンを教えておけば、子どもが練習問題を解きやすくなりますよ。
(例)
あなたに会えて
to meet you
その知らせを聞いて
to hear the news
(3) 文全体の作り方を教える
最後に、「あなたに会えてうれしい」など、文全体の作り方を教えます。
このように教えるべきことを小分けにすれば、勉強が苦手な子も文を作りやすくなるでしょう。
副詞的用法(「感情の原因」)の教え方をもっと詳しく知りたい方は、「不定詞「感情の原因」を分かりやすく教える方法とは?」をご覧ください。
形容詞的用法(~するべき)
勉強が苦手な子に教える場合、次のような解説はオススメしません。
形容詞的用法では不定詞が名詞を後ろから修飾する。
勉強が苦手な子は、こういう解説を聞いてもややこしく感じられるでしょう。
というのも、国語の時間に習う「修飾・被修飾の関係」(どの言葉が、どの言葉を説明しているか)をあまり理解していないからです。
そういう子には、「名詞を後ろから修飾する」と解説するより、「“~するべき”は後回し」と教えるほうがオススメです。
〈教え方の例〉
たとえば、「私は、買うべき本がたくさんあります」という文の場合、まず〈I have many books〉とだけ言うよ。
そのあと、「買うべき」〈to buy〉という情報を付け足そう。「~するべき」は後回しね。
このように、「“~するべき”という情報はあとで付け足す」と教えるのです。
これなら「修飾・被修飾の関係」がわからない子でも理解できます。それに、単語を並べる順番も意識しやすくなりますよ。
形容詞的用法の教え方をもっと詳しく知りたい方は、「中学英語|不定詞(~べき・~ための)を教えるときのコツ4つ」をご覧ください。
名詞的用法
名詞的用法では、問題集によく出てくる文の「パターン」と「訳し方」をまるっと教えるのがオススメです。文法を細かく解説すると、かえってゴチャゴチャすることがあるからです。
たとえば、
〈want to ~〉は、もともと「~することを欲する・望む」という意味。言いかえると、「~したい」という意味になる。
……と細かく説明した場合、勉強が苦手な子はかえって混乱することがあります。
「~したい / ~することを欲する / ~することを望む」のうち、結局どれを使えばいいのか? それが分からなくなるのです。
ですので、「〈want to ~〉というカタマリで、“~したい”という意味だよ」と教えたほうが、子どもが理解しやすくなります。
名詞的用法の教え方をもっと詳しく知りたい方は、下の記事をご覧ください。
まとめ
この記事では、不定詞を教えるときのポイントを3つご紹介しました。
●用法の名前を教えるのは後回しにする
→まずは「訳し方」や「文の作り方」にフォーカスする。
●「何を学ぶのか」を平たく説明する
→「どんな文を作るのか」を子どもがイメージできるように、具体的に説明する。
●ウォーミングアップをする
→〈to + 動詞の原形〉というカタマリに慣れてもらう。
よかったら中学生に教えるときの参考にしてみてください。
使いやすい基礎問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。
また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
********
「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。