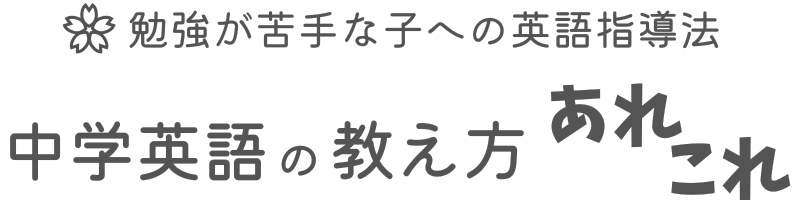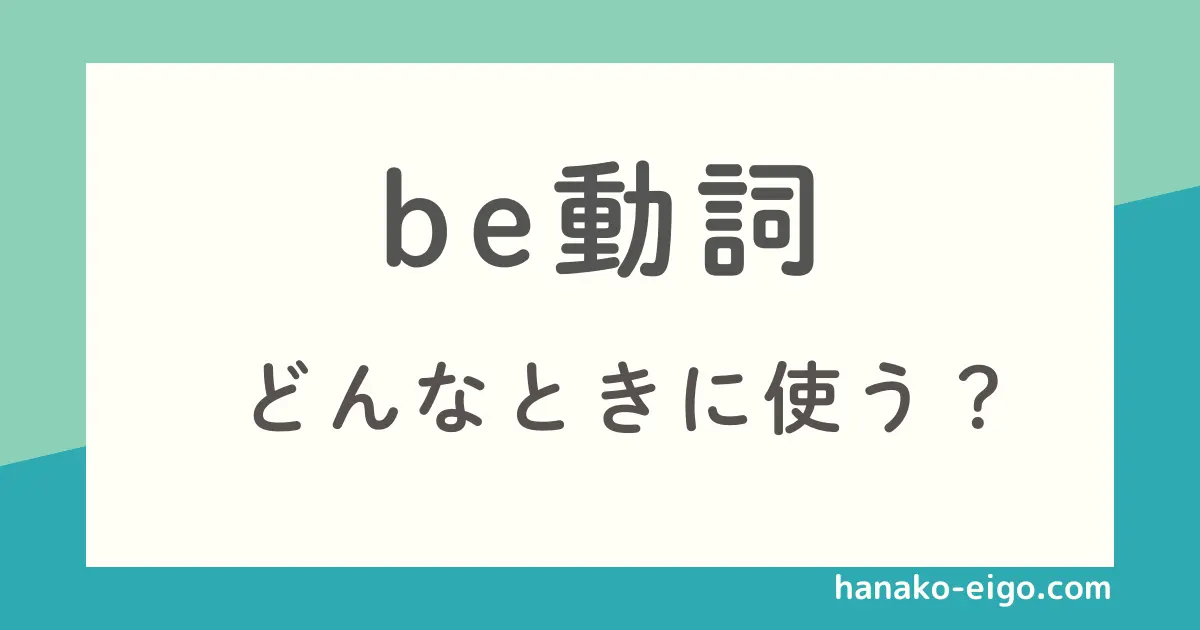どんな文を書くときにbe動詞を使うのか。あるいは使わないのか。
この「be動詞っていつ使うの」問題に頭を悩ませている中学生は少なくないでしょう。
では、そんな子どもたちに「be動詞を使う・使わない」のルールをどのように教えればいいのか? その方法をご紹介します。
まず「子どもたちがbe動詞をきちんと使えない原因」を挙げ、そのあと「be動詞を使うケースの教え方」について説明しますね。
be動詞をきちんと使えない原因
なぜ子どもたちは be動詞をきちんと使えないのか? その原因として次の3つが考えられます。
(1)
「英文には be動詞か一般動詞、どちらかひとつ必要だ」ということを知らない。また、be動詞と一般動詞の使い分け方を理解していない。
(2)
〈I am〉〈you are〉などをカタマリとして覚えてしまっている。例えば I が出てきたら反射的に am をつけてしまう。
(3)
進行形を〈be動詞+ing〉ではなく、単に〈ing〉と覚えてしまっている。同様に、受け身(受動態)を〈be動詞+過去分詞〉ではなく、単に〈過去分詞〉と覚えてしまっている。
では、上のような子どもたちに、「be動詞を使うケース」をどうやって教えればいいのでしょう?
「be動詞を使うケース」の教え方
私がオススメするのは、「be動詞を使うケースは3つある」と教える方法です。
- 動作がないとき
- 進行形
- 受け身
それぞれのケースの教え方を見ていきましょう。
1. 動作がないとき
「動作がないときは be動詞が必要」と子どもに教えます。
その際「動作がないときは……」と話し始めると、ちょっと唐突ですよね。そこで「そもそも動作とは何か」という話から始めます。
〈教え方の例〉
英文を作るときには、「動作があるか、ないか」をまず考えよう。動作というのは、書く、読む、泳ぐなど「何かをする」ってことだよ。
次に、「動作があるなら一般動詞を使う。be動詞は使わない」と説明します。
〈教え方の例〉
動作があるときは、一般動詞を使うよ。たとえば「私は毎日泳ぐ」という文には動作があるよね。だから一般動詞を使おう。
I swim every day.
一般動詞を使うなら、be動詞の出番はないよ。
× I am swim every day.
主語の後ろには、動詞をひとつだけ書こう。一般動詞を使うときは、be動詞をつけたらダメだよ。
最後に、「動作がないときはbe動詞が必要」と教えます。
〈教え方の例〉
happy(うれしい)、interesting(おもしろい)など、動作がないときはbe動詞が必要だよ。
たとえば「この本はおもしろい」という文には動作がないよね。だからbe動詞を使おう。
This book is interesting.
●「一般動詞と be動詞の使い分け方をどう教えるか?」についてもっと詳しく知りたい方は、「一般動詞とbe動詞の使い分け方。中学生に教えるには?」をご覧ください。
●「基本的な語順」の教え方に興味のある方は、「【中1英語】語順の教え方|基礎を教えるための4ステップ」をチェックしてみてください。
2. 進行形
進行形は〈ing〉のイメージが強すぎるため、be動詞が忘れ去られる、ということがよくあります。
そこで子どもに教えるときには、〈be動詞+ing〉というカタマリを強調するのがポイントです。
〈教え方の例〉
進行形を作るときにもbe動詞が必要だよ。進行形の場合は動作があるけど、be動詞が必要なんだ。
(例)He is eating lunch.
進行形を作るときは、必ず〈be動詞+ing〉というカタマリを使おう。〈ing〉だけでは作れないよ。
× He eating lunch.
進行形は〈ing〉じゃなくて、〈be動詞+ing〉だよ。
「動詞はひとつだけ」というルールについて
「主語の後ろに動詞はひとつだけ置く」というルールを習うと、〈be動詞+ing〉というカタマリを見て混乱する子がいます。動詞が2つ(つまり be動詞と一般動詞)並んでいるように見えるからです。
そこで、次のように説明を補足してみてください。
〈教え方の例〉
主語の後ろには、動詞をひとつだけ置くよ。でも進行形の場合、be動詞と一般動詞が2つとも使われているように見えるよね。
(例) They are eating lunch.
じつは、ing形は動詞っぽく見えるけど、動詞ではないんだよ。動詞が ing形に変身すると、もう動詞とは見なされないんだ。
だから進行形の場合、動詞が2つ使われているわけじゃないよ。
3. 受け身
進行形と同じように、受け身についても、〈be動詞+過去分詞〉というカタマリを強調して教えるのがポイントです。
〈教え方の例〉
受け身の文を作るときにも be動詞が必要だよ。
(例) This picture was taken yesterday.
受け身の文を作るには〈be動詞+過去分詞〉というカタマリが必要だよ。過去分詞だけではダメなんだ。
× This picture taken yesterday.
「動詞はひとつだけ」というルールについて
進行形と同じように、受け身の文も動詞が2つ並んでいるように見えますよね。そこで、次のように説明を補足してみてください。
〈教え方の例〉
受け身の文も、be動詞と一般動詞が2つとも使われているように見えるよね。
(例) This picture was taken yesterday.
過去分詞の見た目は確かに動詞っぽいけど、役割は全然違うんだよ。だから過去分詞は動詞とは見なされないんだ。まったくの別物なんだよ。
つまり受け身の文は、動詞が2つ使われているわけじゃないんだ。
「学習内容をアウトプットする機会」を作る
「be動詞を使うケース」を3つ教え終わったら、その内容を子どもが覚えているかチェックしてみてください。次のように、不意打ちの(?)質問をし、「学んだことをアウトプットする機会」を作るのです。
「be動詞を使うケース」は3つあったね。be動詞はどんなときに使うんだったかな?
学びっぱなし(=インプットだけして終わり)では、教わった文法をすぐに忘れてしまいます。知識を定着させるには、学んだ内容を自分で説明してみる(=アウトプットする)という作業が必要です。
もし子どもがうまく説明できなくても構いません(不意打ちの質問に、よどみなくスラスラ答えられる子のほうが少ないですよね)。大事なのは、学んだことを思い出そうとするプロセスです。
「えっと、なんだったっけ……」と思い出そうとする。そのプロセスがあると、正解を聞いたときに記憶に残りやすくなります。
「学んだ内容を自分で説明してみる」という機会を、ぜひ作ってあげてくださいね。
まとめ
「be動詞って、どんなときに使えばいいの?」と疑問に思っている子には、次の3つのケースを教えてみてください。
- 動作がないとき
- 進行形
- 受け身
進行形と受け身については、be動詞を抜かして文を作ってしまう子もいます。ですので、〈be動詞+ing〉や〈be動詞+過去分詞〉というカタマリで覚える、というのがポイントです。
関連記事のご紹介
●「受け身の教え方を知りたい」という方は、「受け身(受動態)の教え方。基礎を教えるための5ステップ」をご覧ください。
●進行形の教え方について興味のある方は、下の記事をチェックしてみてください。
【現在進行形の教え方】現在形との違いを中学生に説明するには?
●「英語の語順はどう教えればいいの?」とお悩みの方には、「【中1英語】語順の教え方|基礎を教えるための4ステップ」がオススメです。
使いやすい基礎問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。
また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
********
「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。