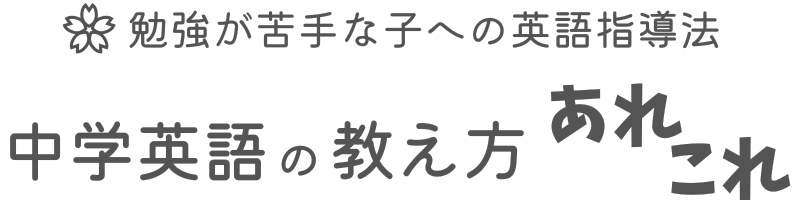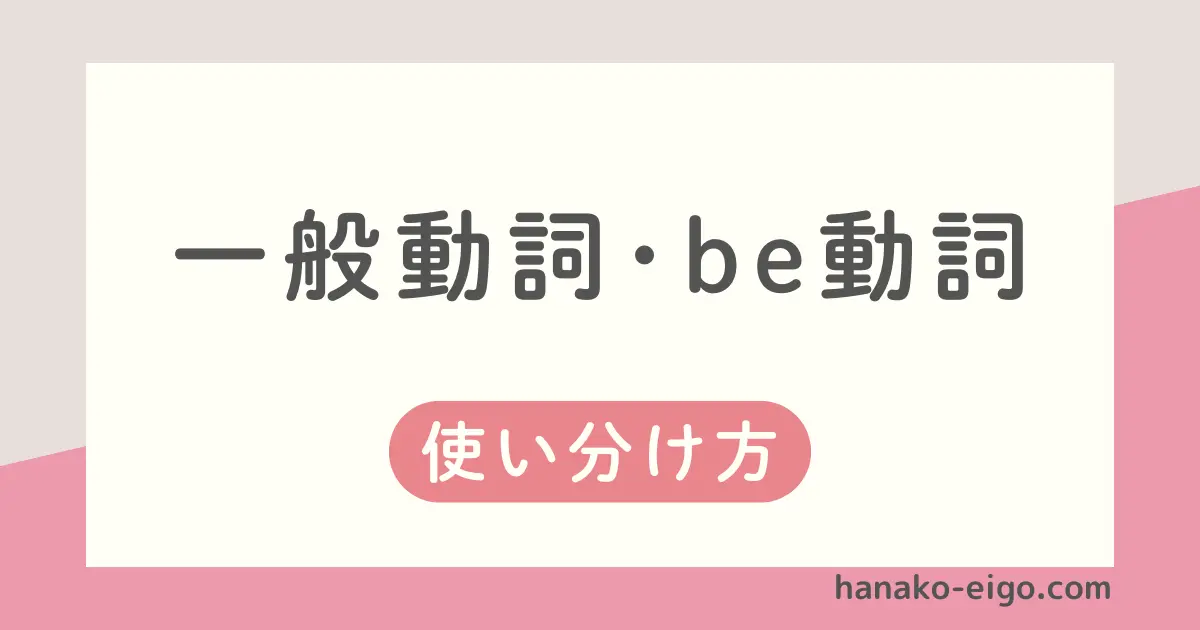一般動詞と be動詞の使い分けができない中学生に、どうやって使い分け方を教えるか? その方法をご紹介します。
難しい言葉を使わずに説明すれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなりますよ。
使い分け方を教える手順
一般動詞と be動詞の使い分け方は、下の順番で子どもに教えます。
- 「どんなときに一般動詞を使うか」を説明する( be動詞より先に一般動詞の説明をするのがポイント!)
- 「どんなときに be動詞を使うか」を説明する
- 「動詞は1つだけ使う」というルールを教える
- 状態動詞(like, know など)について説明する
1.「どんなときに一般動詞を使うか」を説明する
be動詞より先に一般動詞について説明するのがポイントです。
というのも be動詞は日本語にない概念なので、子どもにとっては理解しづらい言葉だからです。そのため be動詞を先に教えようとすると、子どもは混乱してしまいます。
一方、一般動詞は日本語に訳しやすいため、子どももそれほど抵抗感は持たないでしょう。
何か教えるときには、理解しやすい情報から出していく。そうすれば勉強が苦手な子も付いてきやすくなりますよ。
キーワードは「動作」
一般動詞は(基本的に)動作を表す言葉です。そのことを子どもに教える前に、そもそも「動作」の意味を子どもが理解しているか、確認しておきましょう。
「いまいち分かっていない」という子も意外といるので、次のように質問してみるのがオススメです。
〈質問の例〉
英語の授業では、「私は〇〇する」という文をよく作るよね。「〇〇する」ということは、「何か動作をする」ってことだ。
動作というのは、たとえば「食べる」「読む」「行く」などだね。ほかにはどんなものがあるかな?
動作を表す言葉を、子どもにいくつか挙げさせてみてください。簡単に挙げられるように思えますけど、考え込む子もいるのです。
「動作とはどんなものか」を子どもが理解したところで、次のように説明を続けます。
〈教え方の例〉
英語の場合、動作を表すときは一般動詞を使うよ。「食べる」は eat、「読む」は read、「話す」は speak。これらは全部一般動詞だよ。一般動詞は動作を表す言葉なんだ。
たとえば「私は英語を話す」という文を英語に直すとするよ。「話す」というのは動作だから、一般動詞を使おう。
I speak English.
状態動詞の説明は後回し
中学校で習う一般動詞は、ほとんどが動作を表しています。
ですが、中には動作を表さないものもいくつかあります。like や know といった「状態動詞」(状態を表す動詞)です。
こういう状態動詞について子どもに説明するのは、後回しにしましょう。「動作を表すときは一般動詞を使う」という基本を子どもにしっかり覚えてもらうためです。
まずは基本を覚えることに集中。そのあと例外的な状態動詞について学んだほうが、頭を整理しやすくなります。
2. be動詞の特徴を説明する
参考書や問題集には、「be動詞は“状態”や“存在”を表す」という説明がよく載っています。
ですが、勉強が苦手な子に教える場合、「状態」「存在」といった言葉は避けたほうがいいと思います。抽象的で理解しづらいですからね。
キーワードは「動作がない」
be動詞については、「動作がないときは、be動詞が必要」と教えるのがオススメです。
〈教え方の例〉
「うれしい」「大きい」「有名だ」といった言葉には動作がないね。このように動作がないことを表すには、be動詞が必要なんだ。
たとえば「田中さんは有名だ」という文を英語に直してみよう。「有名だ」には動作がないよね。だから、この文を英語に直すときには be動詞が必要だよ。
Ms. Tanaka is famous.
「ある・いる」について説明する
be動詞は、「有名だ」「うれしい」といった「状態」のほかに、「ある・いる」といった「存在」を表すときにも使われます。
「ある・いる」についても、「動作がないのでbe動詞が必要」と教えます。
〈教え方の例〉
「何かがある」「誰かがいる」という場合も、be動詞を使うよ。「ある」「いる」というのは、何か動作を表しているわけじゃないからね。
(例)The book is on the desk. その本は机の上にある。
3.「動詞は1つだけ使う」というルールを教える
動作があるなら一般動詞を使う。動作がないなら be動詞を使う。そう説明したところで、「動詞は1つだけ使う」というルールを教えます。
〈教え方の例〉
主語の後ろには動詞をひとつだけ書くよ。一般動詞か be動詞、どちらかひとつだけね。
両方書いたらダメだよ。逆に、「動詞を何も書かない」っていうのもダメだよ。
私は英語を話す。
× I am speak English.
動詞が2つあるからダメだね。どう直せばいいかな?
田中さんは有名だ。
× Ms. Tanaka famous.
動詞が1つもないからダメだね。どう直せばいいかな?
「どう直せばいいかを子ども自身が説明する」という機会を作ってみてください。教わったこと(インプットしたこと)を身につけるには、自分で説明してみる(アウトプットする)ことが欠かせません。
たとえ子どもの説明が的外れでも大丈夫! 大事なのは、「とりあえず考えてみる」というプロセスです。ひとまず自分で考えたあとに正解を聞いたほうが、断然記憶に残りやすくなりますよ。
4. 状態動詞(like, knowなど)について説明する
一般動詞の中には、動作ではなくて状態を表すものもあります。like や know といった状態動詞です。
状態動詞(like, know など)についても、下のように平たく説明するのがいいと思います。勉強が苦手な子にとって、「状態」という抽象的な言葉は分かりにくいですからね。
〈教え方の例〉
like「好きだ」、know「知っている」、live「住んでいる」といった単語には、「目に見える動作」はないよね。でも、こういう単語も一般動詞に含まれるんだ。
一般動詞ということは、be動詞と一緒には使えないよ。
× I am live in Japan.
文を作るときには、主語の後ろに一般動詞か be動詞、どちらかひとつだけ置こう。
一般動詞の概念を子どもが理解できないときは?
子どもたちの中には、動作を表す言葉(つまり一般動詞)の概念をなかなか理解できない子もいます。
たとえば、busy(忙しい)という単語を見たときに、「あちこち動き回っていろんな動作をしていそうだから、これは一般動詞だ」と考えるのです。
あるいは、teacher(教師)という単語を見て、「先生は手を動かしながら教えるから、これは一般動詞だ」と考えたりもします。
そういう子には、「動作を表す言葉の見分け方」を次のように教えてみてください。
〈教え方の例〉
動作を表す言葉は、最後の音をのばしたときに「う」で終わるよ。たとえば「走る」「書く」の場合、「走るぅ~」「書くぅ~」というふうに「う」で終わるよね。
でも、「いそがしいぃ~」「教師ぃ~」などは「う」で終わっていないから、動作を表す言葉ではないよ。
「う」で終わるものはすべて一般動詞(動作を表す言葉)、というわけではありません。ただ、一般動詞かどうか判断するときの目安にはなります。
まとめ
この記事では、「一般動詞と be動詞の使い分け方」を教える手順をご紹介しました。
- 「どんなときに一般動詞を使うか」を説明する
- 「どんなときに be動詞を使うか」を説明する
- 「動詞は1つだけ使う」というルールを教える
- 状態動詞(like, know など)について説明する
教えるときのポイントは次の3つです。
- be動詞より先に一般動詞の説明をする
- 抽象的な言葉をなるべく使わずに説明する
- まずは基本にフォーカス。例外はあとから教える
少し時間をかけて、じっくり教えてみてくださいね。
オススメ記事のご紹介
→「単語を並べる順番がわからない」「一般動詞とbe動詞を両方使ってしまう」という子に、どうやって英文の作り方を教えればいいか? そのポイントをくわしく解説しています。
→ am, are, is, was, were の使い分け方はどう教えればいいのか? そのコツをご紹介しています。シンプルに教えれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなりますよ。
使いやすい基礎問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。
また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
********
「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。