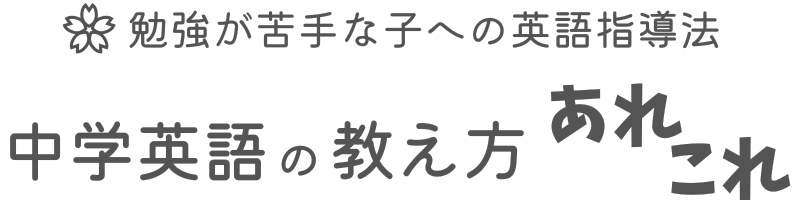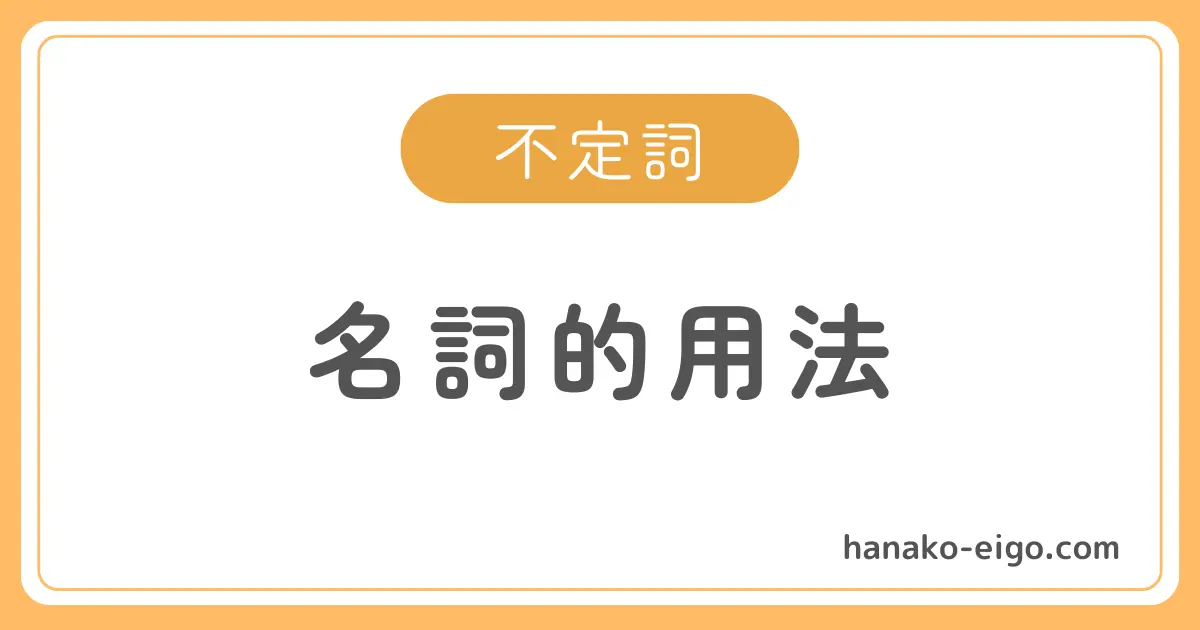不定詞の名詞的用法は(他の用法に比べて)一見シンプル。でも、勉強が苦手な中学生にとっては、つまずきやすいポイントが意外とあります。
そこで今回は、名詞的用法を教えるときの注意点を4つご紹介します。どれもちょっとしたことなのですが、この4つに注意するだけで、勉強が苦手な子も名詞的用法をかなり理解しやすくなりますよ。
「~するのが」という訳も教える
不定詞の名詞的用法は、「~すること」と訳すのが定番ですよね。
(例)
I like to read books.
私は本を読むことが好きだ。
でも、問題集やワークには、「私は本を読むのが好きだ」と載っていることがよくあります。意味としては、「読むことが」と同じですよね。
けれども、同じ意味だということに気づかない子もいます。練習問題を解くときに、「“読むのが”っていうのは、英語で何て言うんですか」と質問したりするのです。
ですので、あらかじめ次のように説明しておく必要があります。
〈I like to read books.〉は、「私は本を読むことが好きだ」と訳すよね。でも、「私は本を読むのが好きだ」と訳すこともできるよ。「~するのが」と「~することが」は、どちらも同じ意味なんだ。
like to / want to / need to などは定番の訳だけ教える
名詞的用法の単元では、次のような熟語が出てきます。( )内にあるのは、定番の訳し方です。
- want to ~(~したい)
- need to ~(~する必要がある)
- like to ~(~するのが好きだ・~することが好きだ)
- start to ~(~し始める)
これらについては、定番の訳し方だけを教えるのがオススメです。どういうことかと言うと、問題集には次のような解説が載っている場合があるのです。
〈want to ~〉は、もともと「~することを欲する・望む」という意味。言いかえると、「~したい」という意味になる。
勉強が苦手な子の場合、こういう解説を聞くとかえって混乱することがあります。「~したい / ~することを欲する / ~することを望む」のうち、結局どれを使えばいいのか、分からなくなるのです。
ですので、定番の訳し方だけを教えるのがオススメです。そのほうが子どもは情報を整理しやすいですし、定番の訳が記憶に残りやすくなりますから。
難しい文法用語はできるだけ使わない
問題集には、次のような解説が載っていることがあります。
不定詞は、文の主語や補語として使われることもある。
【主語】To run is good for your health. (走ることは健康に良い。)
【補語】My dream is to be a teacher. (私の夢は教師になることだ。)
主語や補語の概念が分かっている子に対しては、こういう解説はうまく機能すると思います。
ですが、勉強が苦手な子にとって、主語や補語の概念を理解するのは、かなりハードルの高いことです。
ですので、難しい文法用語はなるべく使わずに教えたほうが、断然理解しやすくなります。
オススメなのは、問題集に出てくる文の「パターン」と「訳し方」をまるっと教えることです。
〈To ~ is 〇〇.〉というカタマリで、「~することは〇〇だ」という意味になるよ。
(例) To speak English is easy.
(このような「不定詞が主語の文」は、実際に使われる英語としては一般的ではありません。でも、問題集ではよくお目にかかります。)
「不定詞が補語になっている文」についても、文の「パターン」と「訳し方」をまるっと教えるのがいいです。
〈XX is to ~.〉というカタマリで、「XXは~することだ」という意味になるよ。たとえば、〈My dream is to ~.〉なら、「私の夢は~することだ」となる。
(例)My dream is to be a teacher.
〈My dream is to ~.〉は、問題集やワークによく出てくる常連さん(?)です。こういう頻出のパターンを教えておくと、文法問題を解きやすくなりますよ。
〈It is …to ~〉は複数のステップに分けて教える
名詞的用法の単元では、次のようなパターンの文も出てきます。
- It is … to ~.(~することは…だ)
- It is … for だれだれ to ~.(だれだれにとって、~することは…だ)
教える側にとって、これらの文はかなりシンプルですよね。〈…〉や〈だれだれ〉や〈~〉に単語を入れるだけですから。
しかし勉強が苦手な子にとっては、必ずしもシンプルではありません。というのも、覚えるべきことが意外と多いからです。
そこで、これらの文を教えるときには、複数のステップを踏むのがオススメです。覚えるべきことを一気に教えるのではなく、少しずつ、小出しにするのです。
そうすれば、子どもたちも頭を整理しやすくなります。
具体的な教え方については、下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
不定詞〈It is … to ~〉の教え方。勉強が苦手な子も理解しやすい!
まとめ
この記事では、不定詞(名詞的用法)を教えるときの注意点を4つお伝えしました。
【名詞的用法を教えるときの注意点】
●「~するのが」という訳も教える
→ 「~することが」と「~するのが」が同じ意味であることを教える。
●like to / want to / need to などは定番の訳だけ教える
→さまざまな訳し方があるが、定番の訳だけ教える。
●難しい文法用語はできるだけ使わない
●〈It is …to ~〉は複数のステップに分けて教える
→覚えるべきことを小分けにして、少しずつ教える。
よかったら実践してみてください。
関連記事のご紹介
副詞的用法や形容詞的用法の教え方にも興味がある方は、「不定詞(3用法)を分かりやすく教えるためのポイント」をご覧ください。