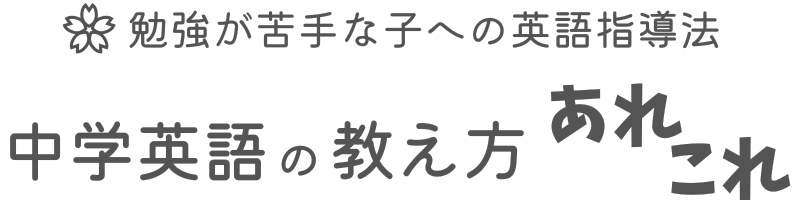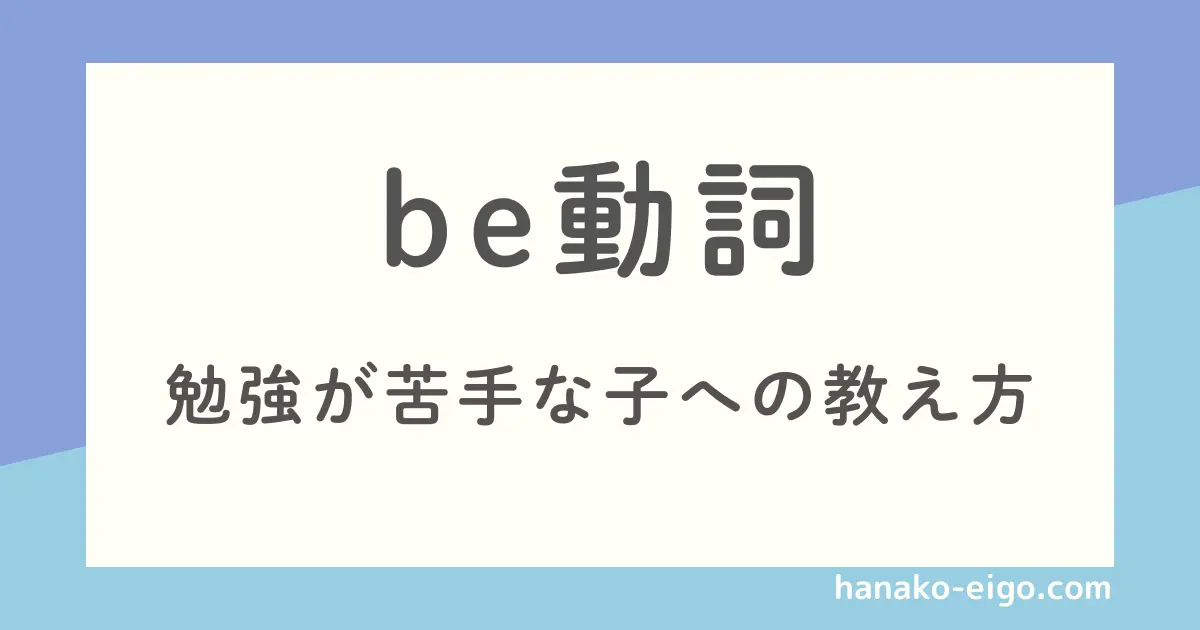「be動詞って、教えるのが難しい!」「どうやって be動詞の意味を説明すればいいの?」
そうお悩みの方に、オススメの教え方をご紹介します。勉強が苦手な子に教えるときの参考にしてみてください。
説明の仕方3パターン
一般的に、be動詞の説明の仕方は3つあります。いずれも、参考書やインターネットによく載っている説明です。
- 説明1 be動詞には「~です・~だ」という意味がある
- 説明2 be動詞には「=」(イコール)の意味がある
- 説明3 動作のないことを表すときは be動詞を使う
この中で私がオススメするのは3番です。これまでに、ほかの2つの方法も試してきたのですが、「勉強が苦手な子に教えるには3番がベスト」と思うに至りました。
では、なぜほかの2つではないのか? 3番の教え方は、具体的にどういうものか? 順にご説明していきますね。
「am, are, is, was, were の使い分け方をどう教えればいいの?」とお悩みの方には、下の記事がオススメです。
「be動詞の使い分け方。勉強が苦手な子に教えるときのコツ」
「~です・~だ」という説明
問題集で、下のような説明を見たことはありませんか?
be動詞には、「~です」という意味がある。〈I am ~.〉なら、「わたしは~です」となる。
中学校の教科書でも be動詞に、「~です(~だ・~である)」という日本語訳が当てられています。
問題点
英語を習い始めたばかりの頃は、「be動詞の意味は、“です”」という考え方で乗り切れます。ですが、すぐに問題が起きてしまいます。
和文の中に「です」がない場合でも、英文に訳すときには be動詞を使うことがよくあるからです。
(例)
私は疲れています。
I am tired.
私たちはおなかがすいています。
We are hungry.
バスが遅れています。
The bus is late.
「be動詞=“です”」と覚えた場合、たとえば〈私は疲れています。〉という文を、〈I tired.〉と訳す子もいるでしょう。和文に「です」が含まれていないので、be動詞を省いてしまうのです。
勉強が苦手な子は、特にそうしがちです。ひとつの日本語に、ひとつの英語を当てはめて文を作る傾向があるからです。
「イコールの意味がある」という説明
be動詞の意味を教えるとき、「=」(イコール)を使って下のように説明する方法もあります。
be動詞には、「=」(イコール)の役目がある。「主語」と「説明の言葉」を「=」でつないでいる。
(例) I = happy. → I am happy.
be動詞の前後がイコールの関係になっている。
「説明の言葉」というのは、文法用語でいうと「補語」。具体的には名詞・形容詞です。
〈I am happy.〉の場合、主語〈I〉と形容詞〈happy〉が、イコール(be動詞)でつながれています。
問題点
繰り返しますが、「説明の言葉」とは、具体的には補語(名詞・形容詞)です。
けれど、それを知らない子どもたちは、補語以外の言葉もイコール(be動詞)を使って主語とつなぐことがあります。
たとえば、〈I am play tennis.〉というふうに、「主語」と「一般動詞」(play)をイコール(be動詞)でつないでしまうのです。
「play は、“I が何をするか”について説明している。だから am でつなぐ」とか、「I が play するのだから、I = play だ」……という理屈です。
「主語の後ろにある単語」が補語(名詞・形容詞)でなくてもイコールでつなぐことができる、と思っているんですね。
かと言って、「イコールでつなぐのは補語(名詞や形容詞)だよ」と教えるのはオススメしません。「補語(名詞・形容詞)」という概念は、勉強が苦手な子にとっては難しすぎますからね。
イコールを使った説明は、「補語」というものをすでに知っている人にとっては説得力があります。
ですが、補語を知らない子にとっては混乱のもとになり得るので、注意が必要です。
「動作のないことを表すならbe動詞」という説明
私がオススメするのは、この方法です。一般動詞との違い(つまり、動作の有無)を強調しながら be動詞について説明する、という方法です。
英文を作るときは、主語の後ろに動詞をひとつだけ書こう。一般動詞かbe動詞、どちらかひとつだけ使うんだ。
「動作」を表すときは、一般動詞を使おう。
(例) 私は毎日牛乳を飲む。→「飲む」というのは動作なので一般動詞を使う。
I drink milk every day.
「動作」がないときは、be動詞が必要だよ。
(例) 彼は幸せだ。→「幸せだ」という言葉には動作がないので be動詞を使う。
He is happy.
「一般動詞と be動詞の使い分け方をどう教えるか?」についてさらに詳しく知りたい方は、「一般動詞とbe動詞の使い分け方。中学生に教えるには?」をご覧ください。
なぜオススメなのか?
「動作がないなら be動詞が必要」という説明は、英作文問題の解説をするときに、とても便利です。
勉強が苦手な子は、英作文問題でよく次のようなミスをします。
- be動詞を抜かして英文を書く (例) They hungry.
- be動詞と一般動詞を同時に使う (例) I am play soccer.
こういうミスに対し、「動作がないなら be動詞が必要」という説明を用いれば、次のように解説できます。
■be動詞を抜かして英文を書いた場合
彼らはおなかがすいています。
(間違い)They hungry.
〈解説の例〉
英文を書くときには、主語の後ろに動詞がひとつ必要だったね。
動作があるなら一般動詞、動作がないなら be動詞が必要だ。hungry には動作がないから be動詞を使おう。
■be動詞と一般動詞を同時に使った場合
私はサッカーをします。
(間違い)I am play soccer.
〈解説の例〉
主語の後ろに動詞をひとつだけ書くんだったよね。でも〈I am play soccer.〉には動詞が2つある。では、どちらを残すか?
動作があるなら一般動詞、動作がないなら be動詞が必要だよ。「(サッカーを)します」には動作があるよね。だから be動詞は使わない。一般動詞の play を残そう。
注意点1(状態動詞)
「動作がないなら be動詞」というルールには、例外があります。動作がないのに一般動詞を使う、という場合があるのです。
どんな場合かというと、like(好きだ)・know(知っている)・live(住んでいる)といった一般動詞を使って文を作るときです。
こういう一般動詞は「状態動詞」と呼ばれ、動作がありません。
状態動詞については、次のように説明を補足してみてくださいね。
〈説明の例〉
like「好きだ」、know「知っている」、live「住んでいる」といった単語には、目に見える動作とか動きはないよね。だけど、like、know、live などは一般動詞に含まれるんだ。
like、know、live などを使うときは、be動詞を一緒に使ってはダメだよ。
× I am live in Japan.
主語の後ろには、一般動詞か be動詞、どちらかひとつだけ置こう。
ただ幸いなことに、中学校で習う一般動詞の多くは、動作を表す「動作動詞」です。
ですので、まずは「動作があるなら一般動詞。動作がないならbe動詞」という基本ルールを覚えてもらう、というのがオススメです。
その上で、like、know、liveなどの例外について補足説明すれば、子どもも理解しやすいでしょう。
注意点2(進行形・受け身)
進行形や受け身(受動態)の場合、動作があっても be動詞を使います。そこで、進行形や受け身をすでに習った子には、「be動詞を使うケース」について説明を補足する必要があります。
【be動詞を使うケース】
- 動作がないとき
- 進行形
- 受け身
詳しい説明の仕方については、「be動詞を使うのはどんなとき? 中学生に教えるときのコツ」をご覧ください。
まとめ
be動詞についてどう説明するか? その方法は、一般的に3つあります。
- 説明1 be動詞には「~です・~だ」という意味がある
- 説明2 be動詞には「=」(イコール)の意味がある
- 説明3 動作のないことを表すときは be動詞を使う
この記事でオススメしたのは、3番です。
「動作がないなら be動詞が必要」という説明の仕方は、英作文問題の解説をするときに、とても役立ちます。
勉強が苦手な子に教えるときの参考にしてみてくださいね。
オススメ記事のご紹介
「単語を並べる順番がわからない」「一般動詞とbe動詞を両方使ってしまう」という中学生に、どうやって英文の作り方を教えるか? どう説明すれば理解しやすくなるか? そのポイントをくわしく解説しています。
使いやすい基礎問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。
また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
********
「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。