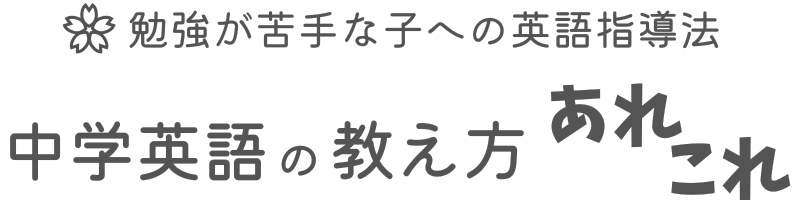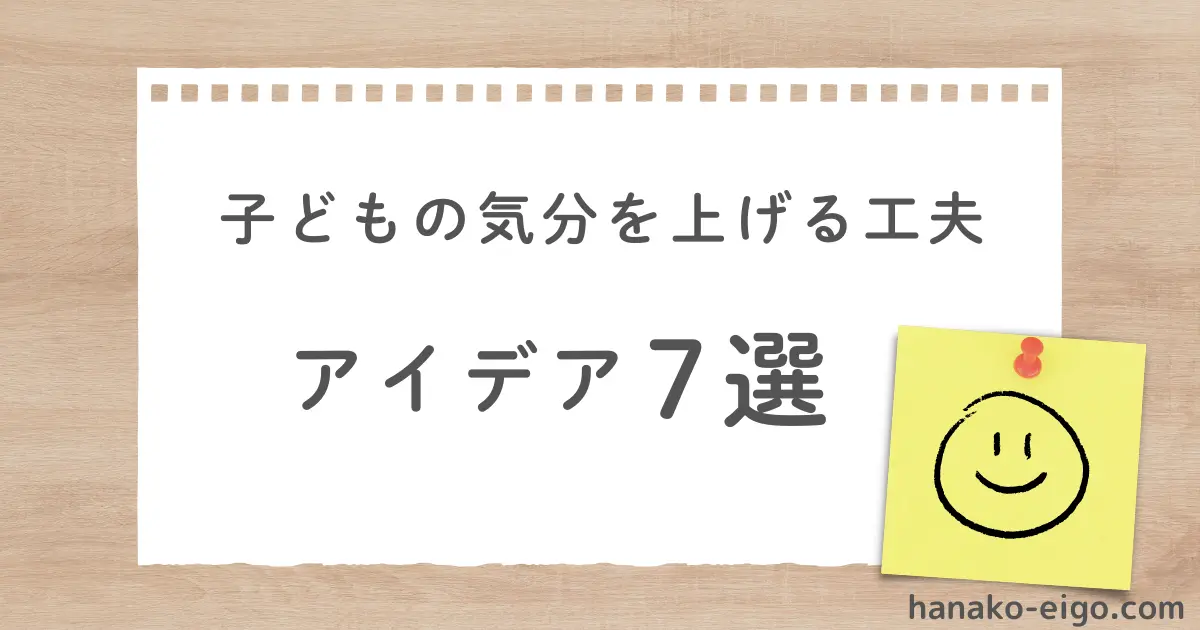生徒の気分が乗らない。集中力がない。そんな日は勉強を教えるのも大変ですよね。
そこでこの記事では、家庭教師や塾講師の方向けに、対処法のアイデアを7つご紹介します。「これは使えそう!」というアイデアがあれば、ぜひ実践してみてください。
最も避けたい対処の仕方
生徒の気分が乗らないとき、教える側が最も避けたいのは「感情的に反応してしまうこと」です。
やる気や集中力のない様子を見ると、ついイライラしてしまいますよね。私もそうです。
でも、そのイライラを顔に出したり声を荒らげたりすると、状況は悪くなるばかり。良いことは何もありません。子どもを委縮させるのがオチです。
子どもは委縮してしまうと、学ぶどころではありません。「いかに怒られないようにするか」を考えるのが最優先になってしまいますから。
そうならないように、教える側は感情的に反応しないようにしたいものです。
そもそも、気分の乗らない日があるのは自然なことです。大人だって365日やる気モード全開の人はいません。
「気分が乗らない日もある」ということを前提に、現実的な対処法を用意しておくのがオススメです。
対処法のアイデア7選
では、どのように対処すれば子どもが少しでも勉強する気になれるか? そのアイデアを7つご紹介します。
どのアイデアも効果てきめん!……というわけではありません(残念ながら)。どれが効くかは、子どもの性格やその日の状態によって異なるでしょう。
ご紹介するアイデアのうち、使えそうなものをいくつか組み合わせてみてください。
選択肢を用意する
練習問題に取り組むとき、どの問題を解くかを子ども自身に選んでもらいます。たとえば英語の場合「並べかえ問題と穴うめ問題、どっちをやる?」などと聞くのです。
子ども自身が選ぶと「やらされてる感」がやわらぎ、取り組みやすくなります。
大人でもそうですけど、一方的にタスクを与えられると押しつけられた感じがして「めんどくさい」と思ったりしませんか?(何かを強制されると、反発したくなるものです。)
強制されたことより、自分で決めたことのほうが取り組みやすいですよね。
それに授業の内容を自分で決めるのは、子どもにとって新鮮でおもしろいに違いありません。「どっちにしようかな」とうれしそうに決める子もいます。そして自分で決めれば、問題に取り組むことへの抵抗感も薄れるでしょう。
説明する機会を作る
練習問題を解いた子に、「なぜその答えになったのか」を説明してもらいます。正解でも不正解でも、そのように答えた理由を子どもが説明するのです。
あるいは、授業で取り上げた重要なポイントを、子ども自身に説明してもらいます。
英語なら「一般動詞に s をつけるのは、どんなとき?」とか、数学なら「円柱の体積の求め方は?」などと質問し、子ども自身が説明するのです。
何かを説明するというタスクは、頭を働かせるきっかけになります。
説明を聞いたり文字を書いたりしているだけだと、いつのまにかボーっとすることがありますよね。でも、何かを口頭で説明するのは、受け身の状態ではできません。意識して取り組む必要があるのです。
口頭で説明しようとすると、ほどよい緊張感も生まれるので、ボーっとしにくくなるでしょう。
クイズ形式を取り入れる
授業にクイズのようなノリを取り入れると、興味を示す子もいます。
(例1)「2秒で考えよう」
子どもに何かたずねるとき、「今から質問するよ。2秒で考えてパッと答えてね」と言います。クイズ番組っぽく、少し軽いノリで盛り上げるのです。(淡々と言うと、なんだか怖い授業になるのでご注意ください。)
秒数は3秒でも5秒でもかまいません。要は、クイズのようなノリを取り入れるのです。そうすると、やる気を見せる子もいます。「制限時間内に問題をクリアしてみせるぞ」と張り切るのでしょう。
この「2秒で考えよう」クイズは、負けず嫌いな子に向いていると思います。ただし、中には軽いノリが合わない子もいます。子どもの性格を見極めた上で、試してみてください。
(例2)「ヒント小出し作戦」
何か質問されて答えられなかった子に、ヒントを出します。その際、いきなりヒントを提示するのではなく、前フリとして「じゃあ、ヒントを出すよ~」と盛り上げましょう。
たったこの一言でクイズっぽい雰囲気を作れます。子どもも「えっと、何だっけ、何だっけ……」と頭を働かせ始めます。
もし子どもが答えられなかったら、「もう少しヒントがいる?」などと言ってから次のヒントを出します。すると、どんどんノッてくる子もいますよ。
大人でもそうだと思いますが、ヒントを小出しにされると「なるべく少ないヒントだけで正解したい!」と妙に燃えませんか?
子どもたちも同じです。「もっとヒントがほしい」とリクエストする子もいます。クイズのようなノリが好きな子には、オススメの方法です。
「やり始めるとやる気が出る」作戦
授業の始めに、ひとまず簡単な問題をいくつか解きます。最初は乗り気ではなくても、解いているうちに不思議と調子が出てくることがあるのです。
「人はイヤなことでも、いったんやり始めるとやる気が出てくる」という話を聞いたことはありませんか?
脳を研究している池谷裕二さんは、次のように述べています。
やる気は、行動の原因ではなく、しばしば行動の結果です。
出典: 池谷裕二『脳には妙なクセがある』、2018年、新潮社
池谷さんによると、何か行動すると、その行動にふさわしい感情が形作られるのだそうです。行動が先で、脳がそれに刺激されるんですね。
このメカニズムを勉強に当てはめると、「とりあえず問題を解くと、勉強する気がわいてくる」となります。
必ずやる気が出るわけではないにせよ、問題を解くうちに調子が出てくる子は、確かにいます。授業の始めはめんどくさそうな様子だったのに、いつのまにか集中して鉛筆を走らせている。そういうことがあるのです。
ですので、授業の始めに練習問題をいくつか解くのも手です。練習問題は、比較的簡単なものがいいでしょう。歯が立たない問題だと投げ出したくなりますからね。
ゴールを明確にする
「あと5分頑張ろう」「あと3問解いたら今日はおしまいだよ」などとゴールを明確にします。
ゴールが見えると乗り切れることって、大人でもよくありますよね。逆に「いつまでこれをやればいいんだろう」という状況は辛いものです。
子どももゴールが見えると、踏ん張りやすくなるでしょう。
子どもの努力に注目する
気分が乗らないときは、机に向かうのにも努力がいります。特に、勉強が苦手な子の場合はそうです。
そこで、子どもに次のような言葉をかけてみてください。
「疲れているのに、よく取り組んでいるね」
「遅くまで勉強するのはきついけど、よく頑張っているね」
「やる気もなくてボーっとしている子を褒めるの!?」と思われるかもしれません。でも、たとえ気分の乗らない日であっても、子どもには「私だって頑張ってる」という気持ちがあるはずです。
その気持ちをくみ取って言葉をかければ、子どもにとって励みになるでしょう。「自分の気持ちをわかってもらえた」と思えますからね。
「ちゃんとしなさい!」と怒られるより、気持ちを理解してもらえたほうが踏ん張りやすくなるものです。
成長した点に気づかせる
「以前と比べてどんな点がよくなったか」を子どもに伝えます。自分の成長に気づいてもらうためです。
自分の成長に気づけば、勉強の手ごたえを感じられます。そして手ごたえがあればこそ、勉強する気になれるでしょう。
子どもに伝える「成長した点」は、ほんの小さな変化でかまいません。むしろ小さな変化を褒められると、大人でもうれしくなりませんか? 「そんなことまで気づいてくれたんだ」と。
ぜひ、小さな変化を見つけてみてください。たとえば、こんな感じです。
・文字を丁寧に書けるようになった
・机に向かうときの姿勢がよくなった
・難しい問題でも、あきらめずに取り組むようになった
・当てずっぽうではなく、きちんと考えて解くようになった
・わからないことがあったとき、質問できるようになった
・重要ポイントをノートにメモするようになった
・【数学】〇〇を求める公式を言えるようになった
・【英語】過去形を書けるようになった
今回は、生徒の気分が乗らない日の対処法を7つご紹介しました。
どれか使えそうなアイデアがあれば、さっそく実践してみてくださいね。最後までお読みいただき、ありがとうございました。