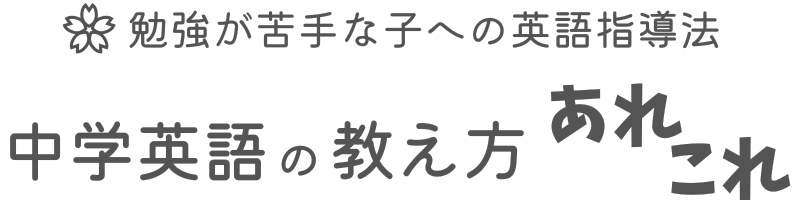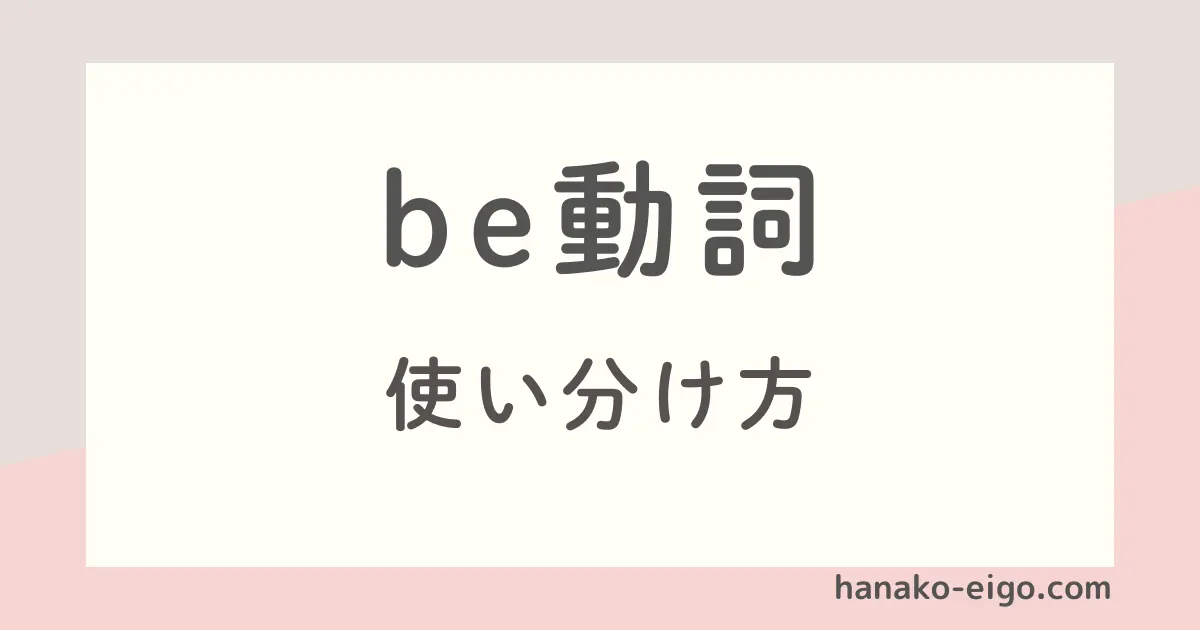be動詞(am, is, are, was, were)の使い分けは、英語を学び始めた子どもたちの多くがぶつかる壁です。
なぜ子どもたちは be動詞を使い分けられないのでしょう?
この記事では、その原因と「使い分け方を教えるときのコツ」を詳しくお伝えします。
「be動詞の意味や役割をどう教えればいいの?」とお悩みの方には、下の記事がオススメです。
be動詞の教え方。勉強が苦手な子に教えるなら、この方法!
be動詞を使い分けられない原因
be動詞を使い分けられない原因は2つ考えられます。
原因1
原因の1つ目は、「be動詞の全体像を把握していない」ということ。
具体的には、「be動詞がいくつあるのか知らない」とか、「am, is, are, was, were は同じ種類の単語だ、という認識がない」などです。
am, is, are, was, were をそれぞれバラバラに覚えてしまった結果、それらを「be動詞」というグループとして把握できていないのです。
原因2
使い分けができない原因の2つ目は、「be動詞の一覧表がやたらと難しく見える」ということ。たとえば、下の表を見てください。
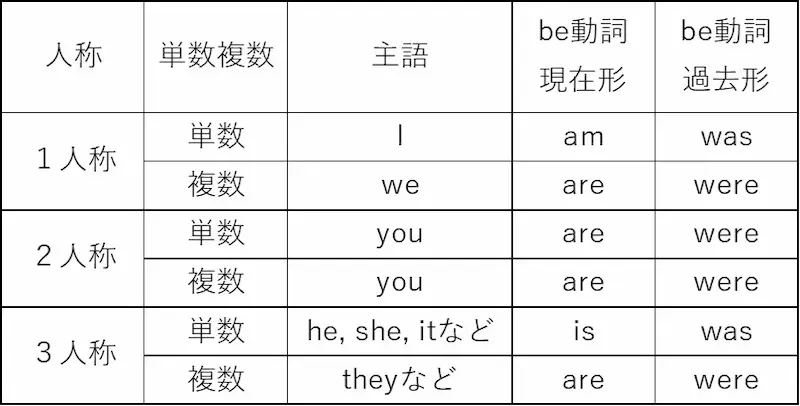
be動詞の使い分けに必要な情報が余すところなく載っている、丁寧な表ですよね。
ですが、この情報の多さが裏目に出る場合もあります。
子どもによっては、この情報量に圧倒されてしまい、どこに注目すべきなのか分からなくなるのです。
上の表は、大人からすると情報が整理されているように見えます。でも子どもにとっては、かえって理解の妨げになるかもしれません。
さて、ここまで「be動詞を使い分けられない原因」を見てきました。では、どのように be動詞の使い分け方を教えればいいのでしょう?
使い分け方を教えるときのコツ
be動詞の使い分け方を教えるときは、説明をシンプルにするのがコツです。
現在形の教え方
下のように教えると、「主語は何人称か?」を考える必要がありません。
| I のとき→ | am |
| you のとき→ | are |
| I・you 以外のとき→ | 単数なら is, 複数なら are |
I am と you are については、まるっと暗記するだけなので、うまく使い分けられる子が多いです。
問題なのは主語が I・you 以外のとき。子どもたちがつまずきやすいのがここです。
主語が I・you 以外のとき
主語が I・you 以外のときは、「主語が単数か複数か考える」というクセをつけないと、be動詞の使い分けはできません。
ですので、次のように強調しながら教えることをオススメします。
「主語が I・you 以外のときには、まず単数か複数かを考えよう。単数か、複数か? まずはそれを考えるんだよ」
「単数か複数か」を連呼して強調すれば、子どもの記憶に残りやすくなるでしょう。
過去形の教え方
過去形は、下のように現在形に関連づけて教えるのがオススメです。
| am と is → | was になる |
| are → | were になる |
これなら、be動詞の一覧表よりスッキリしていますよね。子どもたちも、情報の多さに圧倒されずにすみます。
情報をできるだけ削ぎ落してスッキリさせれば、子どもたちも頭の中を整理しやすくなるでしょう。
とは言うものの、「一度教えればすぐ覚えてもらえる」というわけではありません。子どもによっては、使い分け方が定着するまでに何度も復習する必要があります。
使い分け方を復習するときのポイント
復習のポイントは2つです。
- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)
- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)
具体的にはまず、be動詞の全体像を思い出せるように、次の質問をします。
be動詞は3つあったね。どんなのがあった?
すでに過去形も教えている場合は、下の質問をします。
be動詞の現在形は3つ、過去形は2つあったね。どんなのがあった?
考える機会を作る
ここで大事なのは、「子どもが自分の頭で考える」ということ。即答できなくても構いません。「え~と、なんだったっけ?」と、ひとまず考えてみるのです。
というのも、すぐに正解を教わると記憶に残りにくいからです。苦労せずに簡単に手に入れた答えは、簡単に忘れてしまうもの。ですので、「とりあえず考えてみる」というプロセスが大事です。
結果的に子どもが思い出せなかったら、その時点で答えを教えます。「be動詞は、am, are, is だったね」と。
何段階かに分けて教える
そして、次の質問をします。
主語が I なら、be動詞はどれを使う? 主語が you なら、be動詞はどれを使う?
まずは、I と you だけに注目。この2つについてbe動詞を整理しておきます。その上で、I・you 以外について質問します。
主語が I・you 以外のときは、be動詞をどうやって使い分けた?
こう尋ねると、be動詞を習って間もない子は、きょとんとすることもしばしば。そんなときは次のようなヒントを出します。
I・you 以外のときは、まず主語が単数か複数かを考えよう。単数なら、be動詞はどれだったかな? 複数ならどれだった?
このように、
- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)
- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)
……というのが大事です。復習には時間がかかりますけど、あせらずに教えてみてくださいね。急がば回れ、です。
まとめ
be動詞の使い分け方については、シンプルに説明するのがポイントです。
現在形
→「人称」という用語を使わずに説明します。
過去形
→ 現在形に関連づけて教えます。
情報をできるだけ削ぎ落としてスッキリさせれば、子どもたちも理解しやすくなるでしょう。
復習するときのポイントは次の2つです。
- 考える機会を作る(すぐに答えを教えない)
- 何段階かに分けて教える(一気にガーッと教えない)
be動詞を使い分けられるようになるには、時間がかかるものです。あせらず、じっくり取り組んでみてくださいね。
オススメ記事のご紹介
→ 「単語を並べる順番がわからない」「一般動詞とbe動詞を両方使ってしまう」という子に、どうやって英文の作り方を教えればいいか? その方法をご紹介しています。
使いやすい基礎問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、私が実際に使ってみて「これは使いやすい」と思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも英語の基礎を学びやすい作りになっています。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。出題形式に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方を知りたい」という保護者や家庭教師の方は、この解説を参考にするのもおすすめです。
また、イラストが豊富なので「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
********
「3種類の問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。