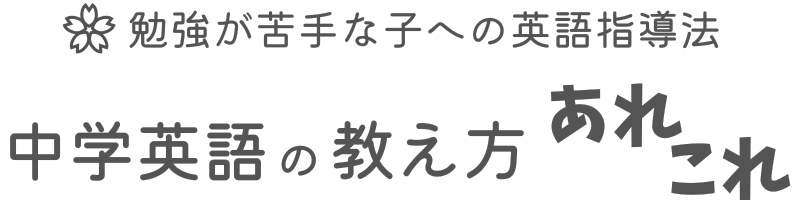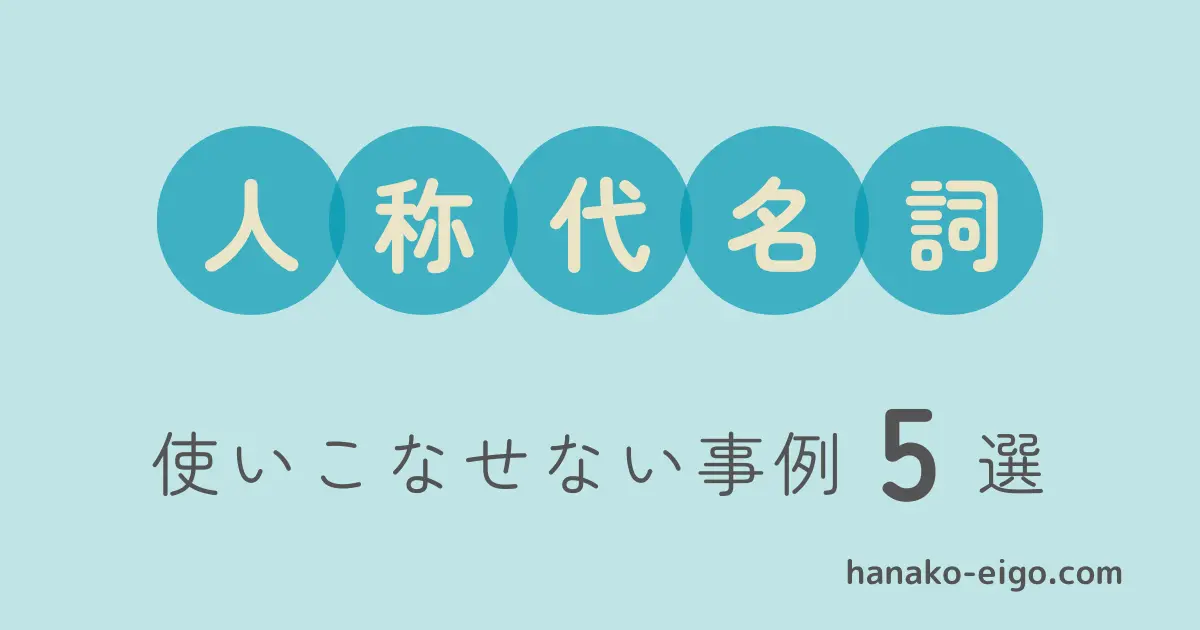中学生が英語の人称代名詞をうまく使いこなせない。その原因は何か? 教える側はどんな点に気をつければいいのか? それについてお伝えします。
具体的には、「人称代名詞を使いこなせないケース」を5つ挙げ、それぞれの原因と対策をご紹介しますね。
「そもそも人称代名詞を覚えていない・覚えられない」というお子さんに教える場合は、下の記事がオススメです。
「人称代名詞を覚えられない中学生への指導法は?」
よかったら参考にしてみてください。
主格しか思い浮かばない
「私の本」を〈I book〉と訳したり、「ケンは彼に会った」を、〈Ken saw he.〉と訳したりする子がいます。
つまり、人称代名詞は主格(「だれだれは」)しか思い浮かばないのです。
原因は?
原因は、日本語を読んだときに、助詞(は・が・の・を・に)に意識が向かないことだと考えられます。
たとえば日本語の文に「私の」と書かれていても、子どもは助詞を気にせず、「私」にだけ反応してしまうのです。
そして、〈I・my・me・mine〉の中で最もなじみのある I が頭に浮かぶのでしょう。
対策は?
日本語の「は・が・の・を・に・のもの」を意識させるために、たとえば、次のようにアドバイスしてみてください。
〈教え方の例〉
「私」が出てきたら、いつでも I を使う、というわけではないよ。「私」の後ろに何があるか、そこに注目しよう。
「私は・私が」なら I を使う。「私の」なら my、「私を・私に」なら me、「私のもの」なら mine を使う。
日本語を読むときには、「は・が・の・を・に・のもの」の部分までチェックしよう。「は・が・の・を・に・のもの」のうち、どれが使われているかで、選ぶべき英単語が変わってくるよ。
「私」だけではなくて、「あなた・彼・彼女・私たち・彼ら」などの場合も同じだよ。
このように説明したら、下のような練習問題に取り組むのがオススメです。説明しただけで終わると、「子どもが理解したかどうか」を確認できませんからね。
日本語と同じ意味になるように、( )に適切な語を入れましょう。
私たちの先生は忙しい。
( ) teacher is busy.
私たちは彼らに会った。
( ) saw ( ).
文中の人称代名詞を認識できない
人称代名詞を正しく書いて一覧表を埋めることはできる。でも文中にある人称代名詞は認識できない。そういう子もいます。
たとえば、一覧表を埋めるテストのとき、〈we・our・us・ours〉と順番に正しく書けたとします。けれど、文中に突然、our という単語がポンと出てくると、「この単語、分かりません」となったりするのです。
そういう場合、「これは人称代名詞だよ」とヒントを出すと、子どもが「……あっ、そうか!」と気づくこともあります。
原因は?
なぜ、こういうことが起きるのか? それは、人称代名詞を覚えたつもりになっているからです。
一覧表を埋めることができると、人称代名詞を覚えたように思えます。
ですが、一覧表を順番に埋めるのは、あくまで「作業」。この作業ができるからといって、人称代名詞が身についたわけではないのです。
対策は?
文中の人称代名詞を認識できるようになるためには、人称代名詞に接する機会を増やすのが一番です。
具体的には、人称代名詞の単元にある、英文和訳の問題に取り組むのがオススメです。
また、何か例文を書いてみせるときに、人称代名詞をバンバン盛り込む、というのも手です。どんな単元の例文であれ、人称代名詞は盛り込めるので、ぜひお試しください。
ちなみに、子どもたちが特に認識しにくい人称代名詞は、こちらです。
●her・hers → hear や here と混同してしまう
●our・us → 読み方も意味も分からなくなる
●their・theirs → there や these と混同してしまう
they を訳すときに混乱する
文中の they が〈モノ・動物〉を受けている場合がありますよね。そういう they をうまく訳せず、混乱する子がいます。
原因は?
they は〈人〉だけではなく、〈モノ・動物〉も表す。そのことを忘れているのが混乱の原因です。
中学英語の場合、they といえば「彼らは(彼女らは)」と訳すのが定番ですよね。
そのため、「they は〈モノ・動物〉も表す」ということを、すっかり忘れている子がいるのです。そういう子の頭の中では、「they = 彼ら」という図式ができあがっているんですね。
そうなると、〈モノ・動物〉を受けている they が文中に出てきたとき、それをうまく訳せません。「これら・それら・あれら」といった和訳が出てこないのです。
対策は?
子どもが they を訳せなかったら、「they は〈モノ・動物〉も受ける」ということを、次のように説明してみてください。
〈教え方の例〉
複数の人を表すときに、they と言うことがあるよね。
それと同じで、複数のモノや動物を表すときにも they を使うよ。モノや動物の場合は「彼ら」じゃなくて、「これら・それら・あれら」という意味になるんだ。
そう説明したら、簡単な例文を子どもと一緒に訳してみます。
(例)I love these books. They are great.
例文には難しい単語は使わず、シンプルなものにしたほうがいいです。そのほうが、要点(つまり、ここでは they)にフォーカスしやすくなりますよ。
日本語の助詞「が」の意味を取り違える
〈I like him.〉ではなく、〈I like he.〉と書く子がいます。like の後ろに、目的格の him ではなく、主格の he を置いてしまうのです。
原因は?
主格の he を使ってしまう原因は、日本語にあります。日本語では「〇〇を好きだ」ではなく、「〇〇が好きだ」と言うため、子どもはその「〇〇が」を主格だと思ってしまうのです。
対策は?
次のように説明するのがオススメです。
〈教え方の例〉
like にはもともと、「〇〇を好む」という意味があるよ。つまり、「彼が好きだ」というのは、もともとは「彼を好む」という意味なんだ。そして、これを英語になおすと、〈like him〉になるよ。「彼を」は〈him〉だからね。
勉強が苦手な子に教える場合は、「like の後ろには主格ではなく目的格がくる」といった説明は避けたほうがいいです。文法用語が抽象的でわかりづらいですからね。
前置詞の後ろに何を置くべきかがわからない
前置詞(at、for、with、of など)の後ろにどんな人称代名詞を置くかを、なんとなく雰囲気で決める子がいます。
原因は?
そういう子は、前置詞の特徴を理解していないと考えられます。その特徴とは、次の2つです。
●前置詞の後ろには目的格を置く(例)with them
●前置詞の後ろであっても、〈所有格+名詞〉を置く場合がある(例)with their teacher
対策は?
前置詞の特徴について、たとえば次のように説明してみてください。「目的格」「所有格」といった用語は使わずに、平たく解説するのがポイントです。
〈教え方の例〉
at、for、with、of などの後ろに人称代名詞を置くときは、注意が必要だよ。
(例)私は彼らと話した。
I talked with ( ).
〈they・their・them・theirs〉のうち、どれを使うかというと、左から3番目なんだ。at、for、with、of などの後ろには左から3番目を使う、というルールがあるんだよ。
子どもが解説を理解したかを確かめるために、練習問題に入ってくださいね。そのあと、〈所有格+名詞〉についての解説を続けます。
〈教え方の例〉
(例)私は彼らの先生と話した。
I talked with ( ) teacher.
この場合は、them じゃなくて their が入るよ。
〈彼らの先生〉というカタマリだけを英語に直してみよう。〈彼らの〉と言うときには、〈they・their・them・theirs〉の左から2番目を使う。「だれだれの」は2番目なんだ。
だとすると、〈彼らの先生〉というカタマリは〈their teacher〉になるよね。文を作るときには、このカタマリごと with の後ろにもってくればいいんだよ。
このように、〈だれだれの〇〇〉というカタマリがあったら、人称代名詞は左から2番目を使おう。
説明したあとは練習問題に入りましょう。子どもが理解しているか確認してみてください。
まとめ
この記事では、人称代名詞を使いこなせない原因を5つ挙げ、その対策をご紹介しました。
〈使いこなせない原因〉
- 主格しか思い浮かばない
- 文中の人称代名詞を認識できない
- they を訳すときに混乱する
- 日本語の助詞「が」の意味を取り違える
- 前置詞の後ろに何を置くべきかがわからない
使いこなせない原因をあらかじめ知っておけば、子どもに解説しやすくなりますよ。よかったら実践してみてください。