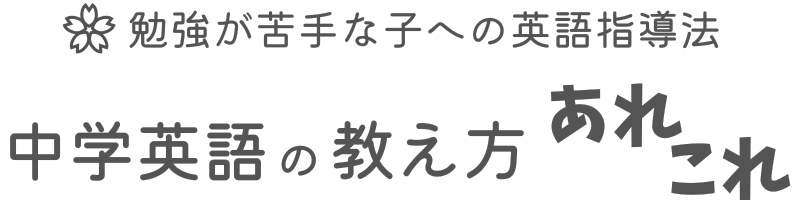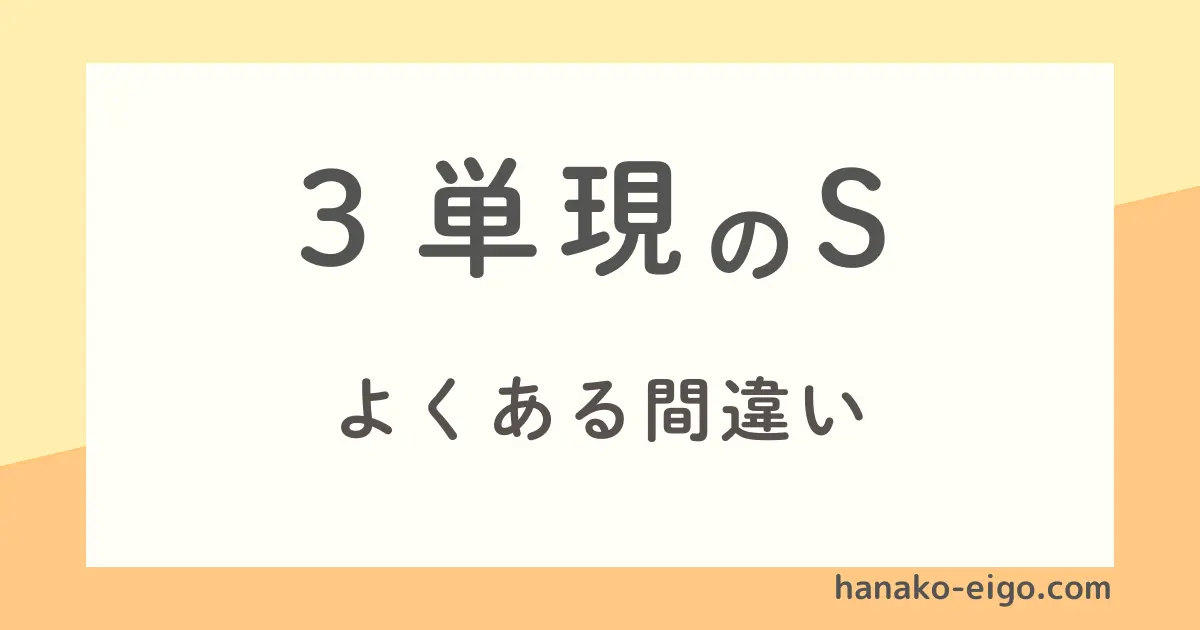どうして「3単現の s」でつまずく子が多いのだろう? そんなふうに不思議に思ったことはありませんか?
子どもたちがつまずくには、それなりの理由があります。では、どんな理由で、どんな間違いをするのか?
その例を5つご紹介し、教えるときの注意点についてお伝えします。
よくある間違いをあらかじめ知っておけば、子どもに文法を解説しやすくなりますよ。
「そもそも3単現の s はどうやって教えればいいの?」とお悩みの方には、下の記事がオススメです。
「3単現のs」の教え方。こう説明すれば中学生も理解度UP
my dogを1人称だと思っている
子どもたちの中には、〈my dog〉を1人称だと思っている子がいます。「私の犬」の中に「私」という言葉が含まれているというだけで、1人称だとみなしてしまうんですね。
このように〈my dog〉を1人称だと思っていると、〈My dog runs fast.〉と書くべきところを、〈My dog run fast.〉と書いたりします。
教え方
そこで、子どもたちには次のように、「私の犬」と「私自身」の違いを説明する必要があります。
〈教え方の例〉
「私」という言葉が含まれていればすべて1人称、というわけではないんだ。1人称は、「私自身」や「私たち自身」のことだよ。
一方「私の犬」は、「私自身」ではなくて「犬」を指しているよね。「私の犬は速く走る」というのは、私自身が速く走るのではくて、犬が速く走る、という意味だね。
ということは、「私の犬」は1人称ではない。3人称ということになる。
〈my dog〉を1人称だと思うのと同様に、〈your dog〉を2人称だと思っている子もいるので、注意が必要です。
「3単現のS」と「複数形のS」を混同している(その1)
「3単現の s」と「複数形の s」のルールを理解していない子がいます。
そういう子は、〈He has a cat.〉とするべきところを、〈He has cats.〉としてしまいます。
これは、「主語が he のときに、一般動詞だけではなく、名詞(cat)にも s をつけてしまう」という間違いです。
こういう間違いをする子は、「s をつける」というルールは覚えていても、「どこにつけるのか」を理解していません。
教え方
子どもたちには次のように、「s をつけるのは一般動詞」と強調して説明する必要があります。
〈教え方の例〉
主語が「3人称単数」で時制が「現在」のときは、一般動詞に s をつけよう。s をつけるのは一般動詞だけ。人や物(名詞)は関係ないよ。
「人称」や「時制」という用語を使わずに、次のように説明するのもオススメです。
〈教え方の例〉
主語が「I・you 以外で単数」、そして「現在」の話をしているときには、一般動詞に s をつけよう。s をつけるのは一般動詞だけ。人や物(名詞)は関係ないよ。
「3単現のS」と、「複数形のS」を混同している(その2)
〈My sisters like pizza.〉と書くべきところを、〈My sisters likes pizza.〉としてしまう子がいます。
これは、「主語に(複数形の)s がついていたら、一般動詞にも s をつけてしまう」という間違いです。
こういう間違いをする子は、「どんなときに一般動詞に s をつけるか」「どんなときに名詞に s をつけるのか」というのを理解していません。
教え方
そこで、「一般動詞につける s」と「人や物(名詞)につける s」の違いを、整理する必要があります。
〈教え方の例〉
人や物(主語)に s がついているからといって、一般動詞にも s をつけたらダメ。〈人や物〉につける s と、一般動詞につける s は、まったく別物だよ。
〈人や物〉に s をつけるのは、複数のとき。〈人や物〉に s がついていたら、「2人(2つ)以上なんだな」ってことが分かる。
これとは別に、一般動詞に s をつけることがある。どんなときかと言うと、主語が「I・you 以外の単数」で、「現在」の話をしているとき。こういうときは、一般動詞に s をつけよう。
he と they を混同している
勉強が苦手な子どもたちの中には、he(彼は)と they(彼らは)とを混同する子もいます。
そういう子は、〈They live here.〉と書くべきところを、〈They lives here.〉と書いたりします。
he と they を混同する原因のひとつは、普段の会話(日本語での会話)にあると考えられます。
子どもたちは普段しゃべるとき、「彼らは」という言葉をあまり使いません。ですので、英語の授業のときだけ「彼らは」という言葉が出てきても、ピンと来ないのでしょう。
教え方
そこで子どもたちには、次のように「彼は」と「彼らは」の違いを説明する必要があります。
〈教え方の例〉
「彼は」と「彼らは」は、見た目はよく似た言葉だけど、意味は全然違うよ。
「彼は」というのは、1人の男性を指している。「彼らは」というのは、2人以上の人たちを指している。「ら」というのは、「たち」という意味だよ。
doesn’t の後ろの動詞を原形にしない
よくある間違いの代表選手と言えば、これ。doesn’t のあとの一般動詞に s をつけてしまう、という間違いです。
たとえば、〈Takuya doesn’t like math.〉とするべきところを、〈Takuya doesn’t likes math.〉としてしまうのです。
教え方
こういう間違いをした子には、「一般動詞を原形にしよう」と解説する必要があります。でもその前に、「原形って何だった?」と質問します。
ここで大事なのは、「考える機会を作る」ということ。いきなり「原形」の解説を始めるのではなく、ひとまず子どもが自分の頭で考えるのです。
そうすることで、「原形」という言葉が記憶に残りやすくなります。
もし考えるというプロセスがなく、子どもが解説を聞いただけだと、おそらく「ふぅ~ん」で終わってしまうでしょう。簡単に手に入れた答えというのは、すぐに忘れてしまうものです。
というわけで、「原形」の意味を復習したあとに、「doesn’t のあとの一般動詞は原形にしよう」と解説する、というのがオススメです。
まとめ
この記事では「3単現の s」にまつわる間違いを5つご紹介しました。
子どもたちが間違うのには、それなりの理由があります。その理由がわからないと、教える側は「なんで間違うの!? ちゃんと復習しなさい!」と怒って終わり……、となるかもしれません。
でも間違う理由が分かっていれば、対策を講じることができますよね。
よかったら、この記事でご紹介した教え方を実践してみてください。