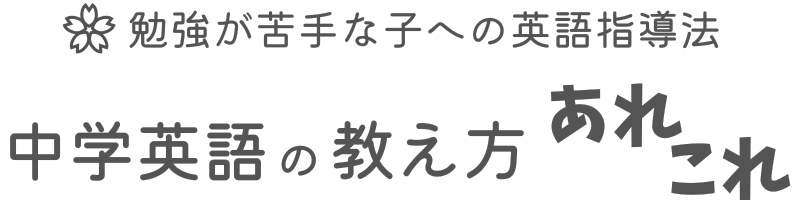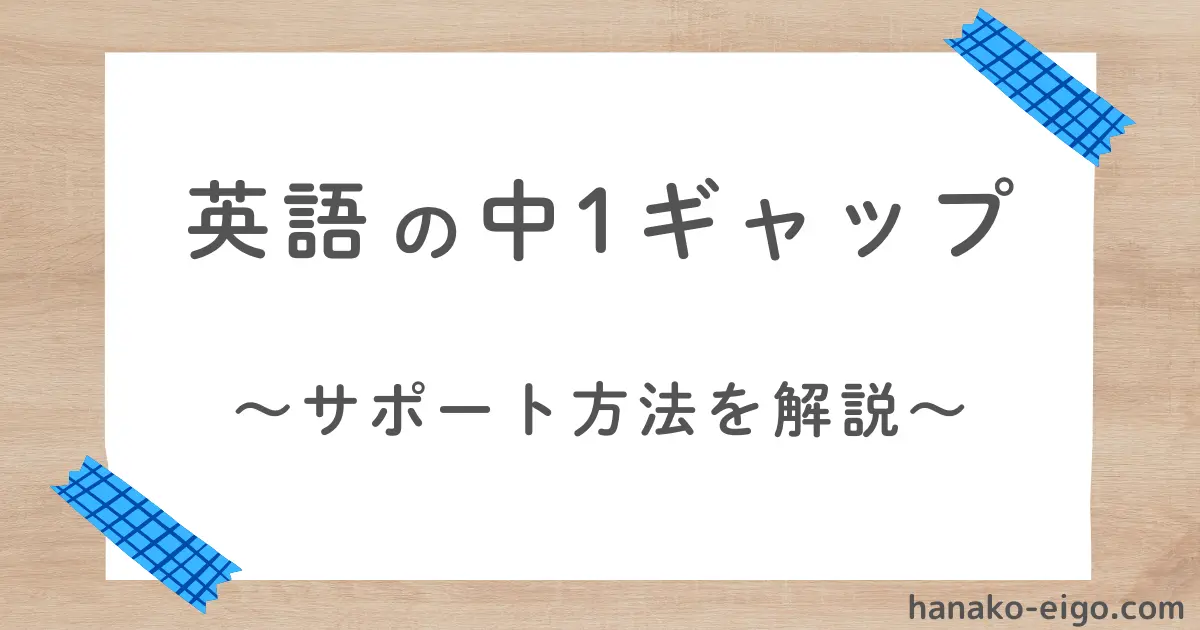「小学生の頃は英語が好きだったのに、中学生になって授業についていけず嫌いになった」
これは英語の「中1ギャップ」「中1の壁」と呼ばれている問題です。「小学生の頃はあんなに英語を楽しんでいたのに……」と心配している保護者の方も多いでしょう。
そこでこの記事では「英語が嫌いになった子をサポートする方法」についてお伝えします。具体的には、下の2つについて見ていきましょう。
- 英語の中1ギャップの「根本的な問題」と、その対処法
- 中1ギャップに陥った子がつまずきやすい点と、その対策
「英語の中1ギャップ」はなぜ起こる?
英語の中1ギャップが起こるのは、「授業内容が小学校と中学校で大きく異なっているから」です。
小学英語と中学英語はまったく別の教科、と言っても過言ではありません。
〈小学英語と中学英語の違い〉
●小学英語
→授業のメインは、ゲームや基礎的な会話などの楽しいアクティビティ。会話をするときは、定型文の空欄に単語を当てはめる。
(例) I like _. Do you like _?
●中学英語
→単語を覚えたり文法を学んだりする。試験では長文もたくさん出題される。
小学校ではゲーム感覚で楽しみながら英語に慣れ親しみます。ところが中学校に入ったとたん、英語が「難しい授業」になってしまうのです。
その結果、授業についていけず英語が嫌いになる、というわけです。
根本的な問題を見落とすな
中1ギャップへの対処法としてよく挙げられるのが、「単語の読み方や文法の基礎を教える」というものです。
もちろん単語や文法は教えないとなりません。けれどもそれを教える1つ前の段階に、中1ギャップの根本的な問題が潜んでいる場合があります。
その根本的な問題を見落としてしまうと、中1ギャップにうまく対処できなくなることがあります。
「英語の中1ギャップ」の根本的な問題とは?
英語が嫌いになってしまう中学1年生は、そもそも下の問題を抱えている可能性があります。
- 「英語にはルール(文法)がある」ということ自体を知らない。
- 「英語はルールを学ぶ教科だ」という認識がない。
これが「英語の中1ギャップ」の根本的な問題です。
「英語にはルールがある」ということ自体を知らなければ、いくらルールを教わっても、それが何を意味しているのかがわかりません。
また、「英語はルールを学ぶ教科だ」ということを知らないまま授業を受けても、つまずいてしまうでしょう。「この授業では一体何が行われているのか」「自分はどこへ向かっているのか」を理解できないからです。
さらに、「ゲームやクイズ、会話を楽しむのが英語という教科だ」と思っている子にとって、中学英語の授業は苦痛に感じられるはずです。
そこで、単語や文法を教える前に、こういう根本的な問題に対処しておく必要があるのです。
どう対処する?
中1ギャップの根本的な問題に対処するには、2つのステップを踏むのがオススメです。
ステップ1. 小学英語と中学英語の違いを説明する
ステップ2. 「文法とは何か」を教える
ステップ1. 小学英語と中学英語の違いを説明する
まず「小学校とは授業の目標が違う」ということを説明しましょう。
〈説明の例〉
小学生の頃は、英語の授業で会話やゲームを楽しむことがよくあったよね。小学校の授業は「楽しみながら英語に慣れる」というのが目標だったんだ。
でも中学校では、授業の目標が変わるよ。「英語の文を読んだり書いたりできるようになる」というのを目指すんだ。
会話もするけれど、文の読み書きにも力を入れる。つまり、小学生の頃とは目指す方向が違うってことだよ。
だから、授業の内容もガラリと変わるんだ。どう変わるかと言うと、「文法」というものを習うんだよ。
上のように説明し、中学英語に対して心構えができるようにしてあげることがポイントです。
ただし「中学英語は難しい」と警告することはオススメしません。「難しい」と言われただけで、英語の授業がイヤになる子もいるかもしれませんからね。
大事なのは「小学校と中学校では、授業の内容が違う」と伝えることです。「難しい」ではなく、あくまで「違う」と説明してあげてください。
ステップ2. 「文法とは何か」を教える
ステップ1では、「中学校では文法というものを習う」と子どもに説明しました。次は「文法とは何か」を教えましょう。
〈教え方の例〉
文法というのは「文のルール」という意味だよ。「文のルール」と言われても、「何それ?」って思うかもしれない。
でもじつは日本語にも「文のルール」があるんだよ。
たとえば「ケーキを食べる」という文を見てみよう。ケーキを食べ終わったら、「ケーキを食べた」となるよね。
「動画を見る」という文の場合、見終わったら「動画を見た」となる。
つまり、終わったことを言うには「た」をつける、というルールがあるんだ。
ふだん私たちが日本語を話すときには、こういうルールに従って文を作っているんだよ。
ルールを意識しているわけではないけれど、じつは日本語のルールをたくさん知っている。そのおかげで会話したり文を書いたりできるんだ。
英語の場合も同じで、ルールがいろいろある。そして、そのルールを覚えれば自分で文を作れるようになる。ルールをたくさん覚えれば覚えるほど、いろんな文を作れるよ。
こういうルールのことを「文法」というんだ。中学校の英語の授業では、文法を学んでいこう。
身もフタもない言い方をすれば、「文法とは文のルールのことで、それを中学校で学ぶ」ということです。
ただ、そんなふうにサラッと言っただけでは、子どももピンとこないでしょう。上のように、日本語の例を挙げながら説明してみてください。
●「英語の中1ギャップ」の根本的な問題
- 「英語にはルール(文法)がある」ということ自体を知らない
- 「英語はルールを学ぶ教科だ」という認識がない
●対策
- 小学英語と中学英語の違いを説明する
- 「文法とは何か」を教える
中1ギャップに陥った子のつまずきポイント
「英語の中1ギャップ」の根本的な問題に対処したあとは、英語の基礎を教えていきましょう。
中1ギャップに陥った子が特につまずきやすいのは、下の2つです。
単語が読めない・書けない
「単語の読み書きができず、授業についていけない」という子は少なくありません。
以前は、中1の授業はアルファベットの練習から始まりました。1学期は単語や簡単な文を書くだけだったので、試験の平均点も高かったものです。
けれども今は違います。中学校では単語の練習にあまり時間をかけません。「小学校で練習してきた」という前提で授業が進むのです。
ところが実際は、小学校でも「単語の読み方や書き方をじっくり教わる」という機会は、あまり多くはありません。
そのため、読み書きができないまま中学生になり「授業の内容を理解できない」という問題が起きてしまいます。
対策は?
対策としては単語の読み書きの練習となりますが、「読み書きの練習」と一口に言っても、やるべきタスクは山ほどあります。
そこで、単語を書いて覚えるのはひとまず横に置いておき、まずは読む練習にフォーカスしましょう。
読む練習と書く練習をいきなり同時に始めるのはオススメしません。
子どもが「自分にはムリ」とあきらめてしまわないように、タスクを小分けにして少しずつ取り組みましょう。
最初は読む練習だけに集中し「読めた!」という自信をつけることが大事です。手ごたえを得られればこそ、「もっと挑戦してみよう」という気になれますからね。
単語をいくつか読めるようになってから書く練習に入ったほうが、子どものやる気を維持しやすいです。
単語の読み方・書き方(覚え方)を教える具体的な方法については、下の記事をチェックしてみてください。
●英単語の読み方。ほとんど読めない子に読み方を教えるときのコツ
●英単語の覚え方を教える方法。勉強が苦手な子が覚えられない原因は?
一般動詞とbe動詞を使い分けられない・語順がわからない
中学生にとって、一般動詞とbe動詞の使い分けは「楽勝!」とはいきません。どの世代にも、苦戦した記憶のある方がいるでしょう。
ですが、とりわけ現在の中学1年生にとっては、これまで以上に難しく感じられるはずです。
というのも一般動詞とbe動詞を同時進行で教わるからです。
一般動詞とbe動詞はルールが異なります。その異なる2つのルールを一度に覚えないとならないのです。
これは例えるなら、アンパンやカレーパンを見たことも食べたこともない人が、2つの作り方を同時に教わるようなものです。
あっという間に2つのレシピが頭の中でごちゃ混ぜになるでしょう。
あんこに玉ねぎを混ぜ込んだり、カレーパンにゴマをトッピングしてみたり……。もはやカオスですね。何を作っているのか、自分でもわからないはずです。
中学1年生も同じです。一般動詞とbe動詞のルールがごちゃ混ぜになり、下のような文を書くことがよくあります。
× I am play tennis.
× I happy.
対策は?
「一般動詞やbe動詞を使うのは、それぞれどんな場合か」を子どもに説明しましょう。
その際、be動詞より先に一般動詞について説明するのがオススメです。
be動詞は日本語にないため、子どもにとって「つかみどころのない存在」です。理解するのは簡単ではありません。
一方、playやreadといった一般動詞は日本語に訳しやすいので、子どももそれほど抵抗なく理解できます。
そこで、まずは一般動詞を使うケースを教え、それを足掛かりにしてbe動詞の使い方を説明しましょう。
〈教え方の大まかな流れ〉
「動きがあること」について言うときは一般動詞を使う、と教える。
↓
「一般動詞の文」に慣れるための練習に取り組む。
↓
「動きがないこと」(happy, busyなど)について言うときはbe動詞が必要、と教える。
↓
「be動詞の文」に慣れるための練習に取り組む。
このように、理解しやすい一般動詞を先に教え、それと比較する形でbe動詞を教えます。
くわしい教え方については、下の記事をチェックしてみてください。
→ 「語順の基礎」の教え方を解説しています。子どもにとって比較的理解しやすい「一般動詞の文」を先に教え、それを足掛かりにして「be動詞の文」を教える、というメソッドです。
→ 一般動詞とbe動詞の使い分け方や、「主語の後ろには動詞を1つだけ置く」というルールの教え方をご紹介しています。
→「動作がないならbe動詞が必要」と説明する方法を取り上げています。
→「am, are, is, was, wereの使い分け方をどう教えるか」について解説しています。
●Do you~?とAre you~?の使い分け|中学生への教え方【試験対策】
→ 試験対策としての「使い分けのテクニック」をご紹介しています。
まとめ
この記事では、「中1ギャップで英語嫌いになった子をサポートする方法」についてお伝えしました。
中1ギャップに悩んでいる子どもたちは、次のような根本的な問題を抱えている可能性があります。
- 「英語にはルール(文法)がある」ということ自体を知らない。
- 「英語はルールを学ぶ教科だ」という認識がない。
まずは、こういう根本的な問題に対処することが大事です。その上で、単語の読み方や文の作り方を教えてみてください。
オススメの問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、「これは使いやすい」と私が思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも一長一短ではありますが、英語の基礎を学びやすい作りになっています。
よかったら参考にしてみてください。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。文法問題に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方がわからない」という保護者や家庭教師の方が、この解説を参考にしながら教える、というのもオススメです。
イラストが豊富なので、「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
「それぞれの問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。