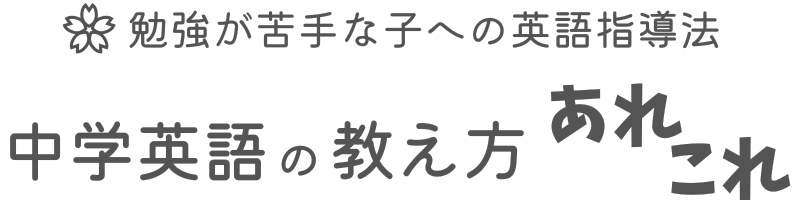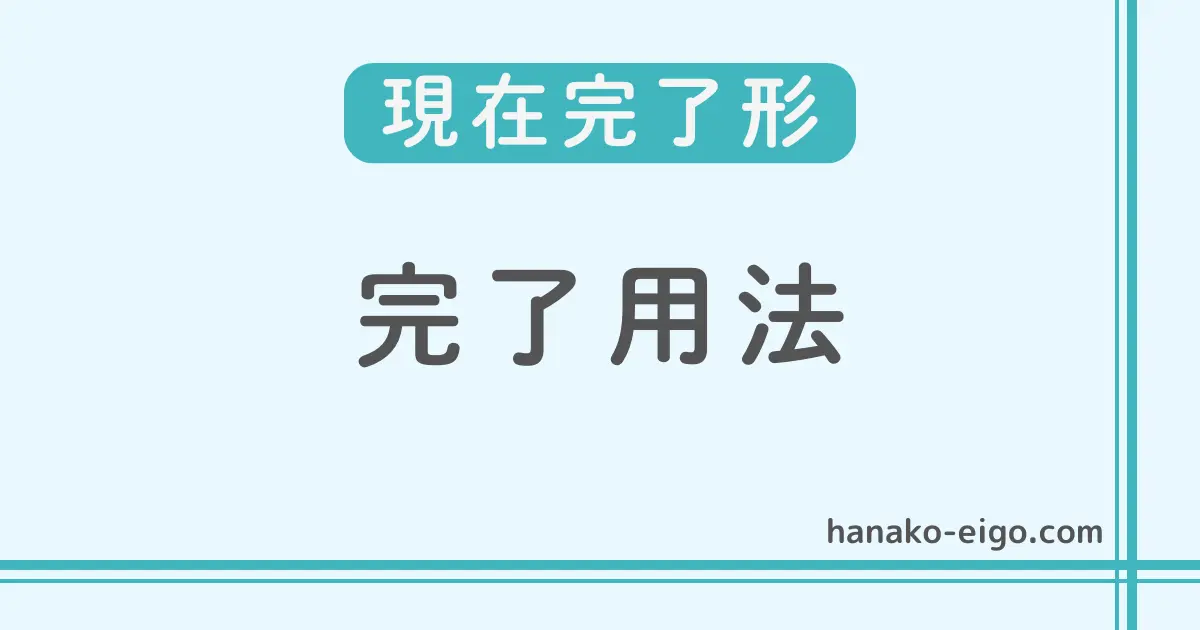勉強が苦手な子に、現在完了形の完了用法をどう教えればいいのか? その方法をご紹介します。
教えるときのポイントは「細分化」。教えるべき内容を小分けにし、少しずつ教えていくのです。そうすれば、勉強が苦手な子も理解しやすくなりますよ。
なお、この記事で取り上げるのは、完了用法の肯定文(平叙文の肯定文)です。
完了用法の否定文・疑問文については、「完了用法(否定文・疑問文)の教え方|勉強が苦手な子への指導法」で解説しています。
「何を学ぶのか」を平たく説明する
まず「今日は何を学ぶのか」を子どもに伝えます。
〈説明の例〉
「~し終えている」「~してある」と表現する方法を学習しよう。
次に、「どんな場面で使う表現か」について、具体例を挙げます。使う場面をイメージできたほうが、完了用法を理解しやすくなるからです。
〈場面設定の例〉
昼食の時間になり、親が子どもに言いました。
親: サンドイッチを食べよう。
子: やった~!
親: 手を洗っておいで。
子: もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)

最後に、上の会話をもとに、「何を学ぶのか」をもう一度子どもに伝えます。
〈説明の例〉
「洗い終えている」「洗ってある」というのは、「手洗いが完了している」ということだよね。
このように、「~し終えている」「~してある」など、「出来事が完了している」と言うための方法を学習しよう。
このくらい具体的に説明すれば、子どもも理解しやすいと思います。
逆に、下のように抽象的な説明で授業を始めるのはオススメしません。
完了用法とは、「動作や状態が現在までに完了している」と伝えるための方法だよ。
こういう抽象的な説明は、大人が聞いてもパッと理解するのは難しいですよね。勉強が苦手な子であれば、なおさらです。
ですので、なるべくシンプルな言葉で具体的に説明してみてください。
過去分詞に慣れさせる
すでに過去分詞を習っている子の場合、(2)に飛んでください。
(1)「過去分詞とは?」を説明する
(2) 完了用法の過去分詞に慣れさせる
「過去分詞とは?」を説明する
「過去分詞とは何か」を説明しましょう。
〈説明の例〉
今回は文を組み立てるときに、過去分詞というパーツを使うよ。過去分詞は動詞が変化したものなんだ。
たとえば「食べる」という意味のeatは、次のように変化する。
原形 eat
過去形 ate
過去分詞 eaten
過去分詞には「過去」という言葉が含まれているけど、「過去」とは関係ないよ。「過去分詞」というのはパーツの名前だと思ってね。
完了用法の過去分詞に慣れさせる
文の作り方に入る前に、完了用法でよく出てくる過去分詞に慣れておくことが大事です。
あらかじめ慣れておかないと、文を作る際、下のように複数のタスクを同時にこなさないとなりません。
- 見慣れない過去分詞を書き写しながら、
- 〈have+過去分詞〉のカタマリを作り、
- 文全体の作り方も覚える
こういうマルチタスクは大変ですので、過去分詞に慣れておくことをオススメします。完了用法でよく出てくる過去分詞を1~2回書いて練習しておくだけでも、文を作るときの助けになります。
完了用法でよく出てくる過去分詞
| 原形 | 過去形 | 過去分詞 |
|---|---|---|
| finish | finished | finished |
| clean | cleaned | cleaned |
| wash | washed | washed |
| read | read | read |
| do | did | done |
| eat | ate | eaten |
| leave | left | left |
〈have+過去分詞〉について教える
基本的な文の作り方について、次の3点を子どもに説明します。
〈基本的な文の作り方〉
●「~し終えている」「~してある」など、「出来事が完了している」と伝えるには、現在完了形を使う。
●現在完了形とは〈have + 過去分詞〉というカタマリのこと。
私は手を洗い終えている(手は洗ってある)。
I have washed my hands.
●現在完了形の have は「持っている」と訳さない。〈have + 過去分詞〉というカタマリ全体で「~し終えている」「~してある」という意味になる。
説明したら文法問題に入りましょう。〈have+過去分詞〉のカタマリに慣れる、というのが目的です。
日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。
1. 私は宿題を終えています。
I _ _ my homework.
2. 私たちは部屋をそうじし終えています。
We _ _ the room.
解答
1. have finished または have done
2. have cleaned
hasを使うケースを教える
have ではなく has を使うケースについて、次の点を子どもに教えます。
〈has を使うケース〉
主語が「I・you 以外で単数」のときは、〈has + 過去分詞〉というカタマリを使う。
ユミは手を洗い終えています(手は洗ってあります)。
Yumi has washed her hands.
「I・you 以外で単数」というのは、「3人称単数」のことです。
「3人称単数」の意味を子どもが理解していない場合、「I・you 以外で単数」と説明したほうがわかりやすいでしょう。
has について説明したら文法問題に入ります。子どもが have と has を使い分けられるか、確認してください。
日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。have と has、どちらを使うかよく考えること。
1. 私の姉は部屋をそうじし終えています。
My sister _ _ the room.
2. 彼らは宿題を終えています。
They _ _ their homework.
解答
1. has cleaned
2. have finished または have done
already と just について説明する
完了用法でよく使われる already と just について、次の2点を子どもに説明します。
〈already と just の説明〉
●「もう~した」「もう~してある」と言うときには、have の後ろに already を置く。already には「もう・すでに」の意味がある。
I have already done my homework.
私はもう宿題をしました。(もう宿題をし終えています。)
● already の代わりに just を使うと「ちょうど~したところだ」という意味になる。
The bus has just left.
バスはちょうど出発したところです。
注意点1
完了用法の訳し方はいろいろあります。そのことについて、子どもに説明しておくことをオススメします。
〈説明の例〉
already や just を使った文の訳し方は、いろいろあるよ。
〈have already 過去分詞〉
→もう~した、もう~してある、もう~してしまった
〈have just 過去分詞〉
→ちょうど~した、ちょうど~したところだ、ちょうど~してしまった
どれも「出来事が完了している」という意味だよ。こういう日本語の文を見たら、どれも現在完了形で表現しよう。
勉強が苦手な子は、1つの語句に対し1つの訳を当てはめる傾向があります。
たとえば、〈have already 過去分詞〉には「もう~した」という訳だけを当てはめてしまうのです。
そのため、「もう~してしまった」という日本文が出てくると、「“してしまった”というのは英語で何て言うんですか」と質問することがあるのです。
ですので「いろんな訳し方がある」ということを、あらかじめ教えておく必要があります。
注意点2
子どもたちは、already や just を置く場所がわからなくなる、ということがよくあります。
否定文を習ったあとであれば、「not を置く場所と同じところに置く」と教えるのも手です。
問題演習の際「already や just を使った文」を大人がリズムよく読んであげる、というのもオススメです。
〈have already〉〈have just〉というカタマリを音で覚えてもらうのです。
もちろん子ども自身が読むのも大事です。ですがリズムよくスラスラ読めなければ、カタマリとして音で覚えるのは難しいでしょう。ぜひ、大人が文を繰り返し読んであげてください。
「already や just は have の後ろに置く」ということを意識するには、下のような文法問題に取り組むのもいいですね。
日本語と同じ意味になるように、下線部に適切な語を入れましょう。
1. 私はちょうど昼食を食べたところです。
I _ _ _ lunch.
2. バスはもう出発してしまいました。
The bus _ _ _.
解答
1. have just eaten または have just had
2. has already left
「完了用法とは何か」を解説する
子どもが文の作り方にある程度慣れたら、「完了用法とは何か? 過去形との違いは何か?」を説明します。たとえば下の2つの違いを教えるのです。
I have already washed my hands.
I washed my hands.
説明の仕方はいろいろあると思いますが、私のオススメは下の方法です。中学生に教えるときの参考にしてみてください。
完了用法と過去形の違い
この記事の最初で出てきた会話を思い出してみましょう。
親: サンドイッチを食べよう。
子: やった~!
親: 手を洗っておいで。
子: もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)
子どもは、単に「洗った」という出来事を報告したかったのではありません。
「洗ってあるからきれいだよ。食べる準備はバッチリ」という意味で、「もう洗ってある」と言った。そう考えるのが自然ですよね。
このように「~したから、今こうなっている」と伝えたいときには、完了用法を使います。
もう洗ってあるよ。(もう洗い終えているよ。)
I have already washed my hands.
ここでは〈I have already washed my hands.〉の中に、「手はきれいだよ。食べる準備はバッチリ」というニュアンスが込められています。
現在完了形が重視しているのは、「(~した結果)今どうなっているか」です。つまり「今」にスポットライトを当てているのです。

一方、過去形の〈I washed my hands.〉からは、「手を洗った結果、今どうなっているか」は読み取れません。(手はきれいなままかもしれないし、もうベタベタに汚れている可能性もあります。)
〈I washed my hands.〉からわかるのは「手を洗った」という出来事だけ。過去形は、過去にスポットライトを当てているのです。
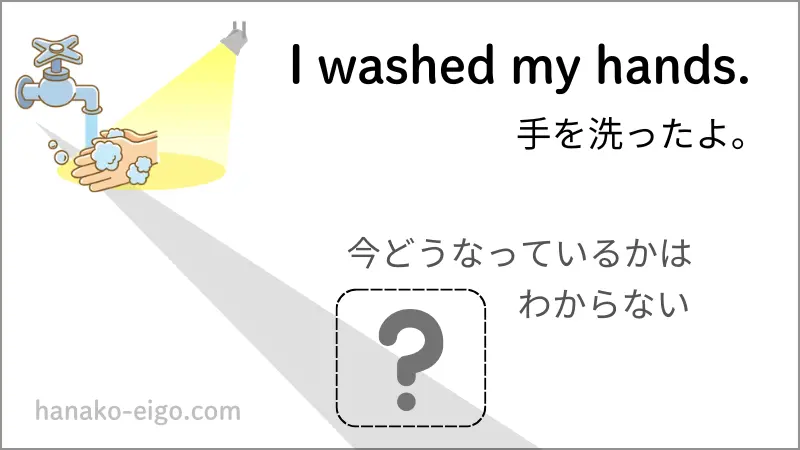
現在完了形(完了用法)
→「~したから、今こうなっている」というニュアンスが込められている。
過去形
→ 終わった出来事について語っている。
現在完了形と過去形の違いについて、もっとくわしく知りたい方は、「現在完了形と過去形の違いを豊富な例文で解説」をご覧ください。
なぜ最初に解説しないのか?
現在完了形の意味や過去形との違いは、授業の最初に解説するのが一般的です。けれども勉強が苦手な子の場合、最後に解説するのをオススメします。
というのも最初に解説した場合、「これから何を学ぶのか」が子どもに伝わりづらくなるからです。
「現在完了形とは何ぞや」という説明は抽象的なので、勉強が苦手な子にとって理解するのは簡単ではありません。
そのため、「これから何を学ぶのか」「どこに向かっているのか」が見えてこないのです。
そして、その状態で解説を聞き続けても、なかなか頭に入ってこないでしょう。
ですので、「現在完了形とは何ぞや」はひとまず横に置いておきます。まずは現在完了形の文を作ることに慣れる、というのを目指すのです。
そして、現在完了形にある程度慣れた時点で、「現在完了形の意味や過去形との違い」の解説に入るのがいいでしょう。
習熟度によっては解説を省く
子どもの習熟度によっては、「現在完了形とは何ぞや」の解説を省くのもアリだと思います。
たとえば過去形の文をパッと作れない子の場合、「現在完了形と過去形の違い」まで理解するのは、かなり難しいのではないでしょうか。
そうであるなら、「現在完了形とは何ぞや」の説明は思い切って省き、文の作り方に集中したほうがいいでしょう。現在完了形の文のパターンに慣れる、というのを目指すのです。
理屈はわからなくても、現在完了形の各用法のパターンを覚えていれば、学校のワークやプリントに取り組みやすくなります。
子どもに勉強を教えるときは、つい、あれもこれも説明してあげたくなりますよね。
けれども、すべてを教えることが必ずしも良いとはかぎりません。子どもの習熟度によって、教える内容に優先順位をつけることも必要です。
まとめ
この記事では、現在完了形(完了用法)の教え方をご紹介しました。
特に大事なポイントは下の3つです。
- 「何を学ぶのか」を具体的に説明する
- 教えるべきことを細分化し、小出しにしながら教える
- 完了用法の意味や過去形との違いは、授業の最後に教える
よかったら実践してみてくださいね。
オススメの問題集3選
書店やネットで英語の基礎問題集を選ぼうとしたけど、たくさんありすぎて、結局どれがいいのかわからなかった……という経験はありませんか?
そこで、「これは使いやすい」と私が思った基礎問題集を3種類ご紹介します。どれも一長一短ではありますが、英語の基礎を学びやすい作りになっています。
よかったら参考にしてみてください。
(1)「ひとつずつ すこしずつ ホントにわかる」(英語)学年別シリーズ(新興出版社)
文法の解説がスッキリまとまっており、要点がパッとわかります。
また、単元によっては練習問題の前に、例題と解答が載っています。これはポイントが高いと思います。文法問題に慣れていない子も「こんなふうに解けばいいんだな」というのがわかりますからね。
さらに並べかえ問題には、パズル感覚で取り組めるような工夫が施されています。
今回ご紹介する3種類の中では、勉強が苦手な子にとって、最も取り組みやすい練習問題だと思います。
↑中2英語・中3英語もあります。(現在完了形は「中3英語」に載っています)
(2)「ひとつひとつわかりやすく。改訂版」(英語)学年別シリーズ(Gakken)
文法の解説がとにかくわかりやすいです。「文法の教え方がわからない」という保護者や家庭教師の方が、この解説を参考にしながら教える、というのもオススメです。
イラストが豊富なので、「文字だけで説明されるより、イラストもあったほうが理解しやすい」というお子さんに向いています。
↑中2英語・中3英語もあります。(現在完了形は「中2英語」と「中3英語」に載っています)
(3)「英文法 パターンドリル」学年別シリーズ(文英堂)
知識を定着させるためのドリルです(文法の解説は最小限に抑えられています)。
各単元で、重要構文が何度も繰り返し出てきます。これぞ、まさに「ドリル」。徹底的に反復練習をしたい、というお子さんにオススメです。
「この単元のキモは何か?」を意識しやすい作りになっています。
↑中2英文法・中3英文法もあります。(現在完了形は「中3英文法」に載っています)
「それぞれの問題集の良い点・注意点をくわしく知りたい」という方は、下の記事をチェックしてみてください。
【徹底比較】英語が苦手な中学生向け基礎問題集3選。使いやすさを比べてみた
最後までお読みいただき、ありがとうございました。